論文のオープンアクセスとは?
2023.04.04
2025.01.17
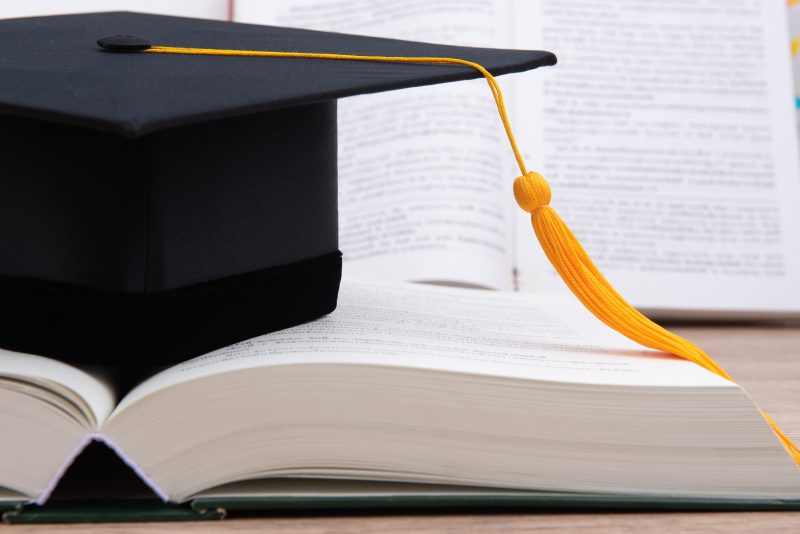
近年、世界的に論文がオープンアクセス化されています。この記事ではそんな論文のオープンアクセス化によるメリットやデメリットなどについて触れていきたいと思います。
オープンアクセスとは
オープンアクセスは、論文などの学術的な情報をインターネット上で無料閲覧かつ誰でも利用できるようにすることです。
論文製作者の設定した条件で再利用することもできます。掲載先や論文掲載料の支払い者によってオープンアクセスは以下の5種類に分けられます。
1.ゴールド
2.グリーン
3.ハイブリッド
4.ブロンズ
5.遅延型
1つ1つ特徴を見ていきましょう。
ゴールド
主に掲載が推奨されているのは、このゴールドです。ゴールドでは、掲載先がオープンアクセス誌となり掲載費用の負担者は著者となります。読み手(大学、図書館などの組織も含む)からは一切購読料を貰わないのが特徴です。
グリーン
購読料を払うスタイルの学術雑誌に掲載された論文のうち、論文製作者自身が並行して機関リポジトリ等に公開した論文を指します。
掲載誌によって、学術雑誌に公開されている論文と同じものが一定の期間経過後に公開される場合や、査読済みの著者最終稿の場合など様々な論文が掲載されているのが特徴です。
著作権の条件は論文によって違うため、再利用などについては論文製作者や著作権者に確認してください。
ハイブリッド
購読誌に掲載されますが、論文製作者が著者支払いを選択し、読み手が購読料を払わなくても見ることができるようになっている論文です。
論文製作者は今までの投稿スタイルを変えずにオープン化できますが、論文の掲載料が高額になりやすいという問題もあります。
ブロンズ
出版社のサイトで無料にて見ることができますが、明確な許諾条件が明示されていない論文です。
出版社の裁量により、一時的に無料で読めるようになっていることが多く例えば、ノーベル賞受賞者の論文を一時的に掲載しているなどの例があります。
許諾条件が明確ではないため、読み手が再利用することはできません。
遅延型
6ヶ月から1年前に購読誌に掲載された論文で、ある程度時間が経ってから公開される論文です。
オープンアクセスのメリット
オープンアクセスに論文を掲載することにはどんなメリットがあるのでしょうか。ここからは、オープンアクセスのメリットについてお伝えしていきます。
世間へ広まりやすい
オープンアクセスは、素早く無制限にアクセスすることが可能なためあっという間に研究の露出が増えてきます。
オープンアクセスでは、論文が無料で公開されるため論文製作者はSNSなどを利用し広く研究の宣伝を行うことが可能です。
露出が高まっていけば、共同研究を行うパートナーの獲得につながったり奨学金や寄付の提供を持ちかけられたり、学会へ招待されたりと様々な交流や資金提供へのきっかけともなるでしょう。
科学研究が一般にも広く普及する
購入しなくては読めないジャーナルなどは、研究者でない一般の人に馴染みがないものです。そのため、科学研究が特定のコミュニティでしか共有されなくなってしまいます。
一方で、オープンアクセスは研究者じゃない一般人でも閲覧可能です。一般の人々を巻き込みながら科学を広く普及させていくことは重要と言えます。カナダなどの助成機関では助成の判断をするメンバーの中に一般人も混じっているので、論文をオープンアクセス化させることは非常に意味のあることなのです。
オープンアクセスのデメリット
オープンアクセスはメリットばかりではありません。ここでは、オープンアクセスのデメリットをご紹介していきます。
悪質なハゲタカジャーナルに投稿してしまう可能性がある
オープンアクセスの出版方法を悪用して、論文の製作者から論文投稿料を取ることだけを目的とし、正しい査読を行わずに何でもかんでもリリースしてしまう悪質な学術誌のことをハゲタカジャーナルと呼びます。
ハゲタカジャーナルに投稿してしまった場合、論文製作者は所属しているコミュニティはもちろん業界内でも著しく研究成果の評価を下げてしまうことになるでしょう。
最悪の場合正式な研究結果として認められず、学術文献のデータベースに収載されなくなってしまいます。
また、未完成な成果がネット上で広まってしまったり突然の閉鎖によりアクセス不能となる可能性もあります。
さらには、撤回に応じてくれない場合もあり他のジャーナルに掲載し直したくても二重投稿となってしまう可能性や相場よりも高額な掲載料を要求されるなど注意が必要です。
まとめ
オープンアクセスは、自らの研究を広く知ってもらうのにかなり有益だと言えます。狭いコミュニティのみでの共有しか可能性がなかったものが、世界中の誰もが閲覧できるというのは研究分野の更なる発展のきっかけにもなるでしょう。
ただし、しっかりと掲載する場所を選んでいかないとせっかくの研究も台無しになってしまうので注意しましょう。
学術大会・国際会議開催システム「アワード」のご紹介
学会運営における課題を解決し、効率的かつ効果的な運営を実現するために、学術大会・国際会議開催システム「アワード」は以下のニーズにお応えします。
-
1. 学会の効率化と人手不足の解消
学会運営では、事務局の業務量が膨大で、少人数で対応するのが難しい場合もあります。学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、煩雑な運営業務を自動化・効率化することで、人的リソースの負担を軽減します。たとえば、参加登録、プログラム作成、講演者管理などがワンストップで完結します。
-
2. 学会運営のコスト削減
学会開催には、印刷物や郵送、事務局人件費など多くのコストが発生します。学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、クラウドベースでの運営によりこれらのコストを大幅に削減可能。さらに、事務局代行費用を削減しつつ、高品質なサービスを提供します。
-
3. 決済機能でスムーズな収益管理
学会参加費や年会費のオンライン決済に対応。安全性の高い決済システムを導入しているため、事務局での入金確認の手間が省け、効率的な資金管理が可能です。これにより、参加者にも事務局にもストレスフリーな学会運営を実現します。
-
4. 学会運営サポートで「大変」を「簡単」に
「学会運営が大変」と感じている学会事務局の方々に向け、運営全般を支援する学会運営サポートをご用意しています。例えば、会場手配、プログラム編成、スポンサー管理など、運営代行サービスもご紹介可能です。
-
5. 柔軟な管理システムで多様なニーズに対応
学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、学会の規模や形式に応じて柔軟にカスタマイズ可能。オンライン学会、ハイブリッド開催にも対応しており、参加者がどこにいても円滑な学会開催をサポートします。
-
6. 費用対効果の高い学会開催を実現
学会開催費用を抑えつつ、質の高い学会運営を目指す方に最適なソリューションです。クラウド型システムの導入で初期費用を抑え、必要に応じて追加オプションを選択することが可能です。
学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、学会の運営をトータルでサポートし、効率化・コスト削減を実現する強力なパートナーです。学会運営の課題を抱える事務局や運営会社の皆さま、ぜひ一度ご相談ください!





