研究論文、学位論文、アブストラクトなどの作成にChatGPTを使うべきなのか
2023.03.20
2025.11.20
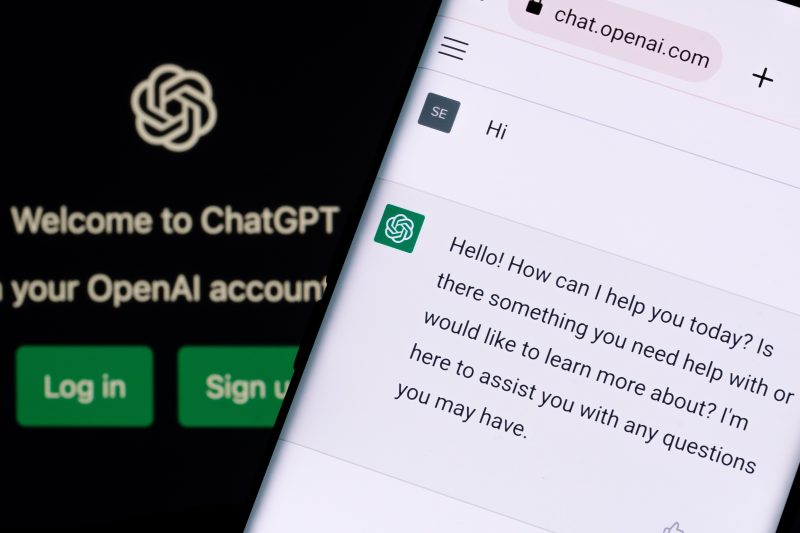
ChatGPTの登場は、様々な業界に影響を与えています。その影響は、学術界も例外ではありません。この記事では、ChatGPTが学術界に影響を大きく与えると考えられるChatGPTを利用した研究論文、学位論文、アブストラクトなどの生成について深掘りしていきたいと思います。
そもそもChat GPTを使うには?
Chat GPTは、現在無料で提供されています。しかもChat GPTは、AIの知識やパソコンスキルなどの専門知識を必要としなくても誰でも簡単に利用することができます。下記にChat GPTの利用開始までの流れをまとめましたので参考にしてみてください。
1. https://openai.com/blog/chatgptにアクセスする
2.個人のアカウントを作成する
3.手順に従ってログインをする
4.ホームページで説明されている注意事項などを確認する
5.Chat GPTの利用画面の下部にあるテキストボックスに知りたいことを書き込む
6.聞いたことがChat GPTから返ってくる
Chat GPTは現在ホームページから使用することができ、アプリ等をダウンロードする必要はありません。現在Chat GPTを名乗るアプリが複数リリースされていますが、それらはChat GPTをリリースしているOpen AI社とは関係がありませんので注意してください。
Chat GPTは研究に役立つのか
Chat GPTが学術研究で役に立つのは、新しいプロジェクトを提案するときや研究で行き詰まった時など新たなアイデアが欲しい時だと考えられます。ただしChat GPTが示してくれた案はしっかりと精査する必要があるでしょう。Chat GPTは、優秀すぎるが故に『よくわかりません』などといった答えではなく嘘でもなんとなくそれっぽい答えを返してきます。そのため、Chat GPTの案を実行するには人間の知性でしっかりとチェックしなくてはなりません。
Chat GPTを研究論文などに利用すべきか
研究論文、学位論文、アブストラクトなどの生成に関してChat GPTなどの高度なAIの技術を使用することについては、様々な議論がなされています。そのなかで出版論文に関して、ジャーナル編集者と出版社はChat GPTを論文の著者として認めることはできないという考えだそうです。
なぜならChat GPTなどの高機能なAIチャットボットは、生成した論文の内容と公正性などについて責任を持つことができないからです。NatureやScience などのジャーナルでは、Chat GPTを利用して論文を作成した場合にChat GPTを使った方法または謝辞の所でChat GPTを利用したということを述べることを推奨しています。
アメリカのニューヨークの公立学校などでは、Chat GPTやそれに類似するツールの使用を禁止する動きがあります。学校に通う生徒がChat GPTを利用して課題やテストの解答を行う可能性があるからです。また、教育機関ではAIが生成した文章か判断するAI検出チェッカーへの関心を高めています。ジャーナルや出版社はすでに剽窃チェッカーや画像処理チェッカーを導入していますが今後AI検出チェッカーを導入することは間違い無いでしょう。
ここまでを踏まえて研究論文、学位論文、アブストラクトなどの生成に関して現段階でChat GPTを使う場合は、論文を書く際の補助的なツールとして使うべきだと考えられます。
Chat GPTを論文作成に利用するポイント
補助的に使うといってもなかなか利用方法が思いつかない場合もあるでしょう。ここでは、利用するポイントについて詳しく解説していきます。
アイデア出し
テーマや目次が決まらない、文章の構成が浮かばないという場合にChat GPTを使うと良いでしょう。Chat GPTに対して『○○というテーマの論文の構成を考えて』と投げかけるとあっという間に論文の構成が作り出されます。
論文の骨組みができあがれば後はそれに沿って肉付けしていくだけなので、1から論文を作るよりも遥かに効率が上がるでしょう。
参考URLまで記載させる
Chat GPTは、優秀すぎるがために嘘でもそれっぽい文章が生成されるという特徴があります。そのため人間が最後にチェックする作業が必要です。参考URLまで記載させておけばチェックの際にそのURLをクリックして確認するだけなので作業効率が上がります。
細分化して質問をする
Chat GPTに対して細分化し質問をすることで精度の高い文章が出来上がります。目次などをChat GPTに作ってもらった後、項目ごとに質問していき繋ぎ合わせていくことで論文や文章の全体を作ることができるでしょう。
注意点としては、細分化して質問したとしてもしっかりとファクトチェックは怠らないようにしてください。
学術大会・国際会議開催システム「アワード」のご紹介
学会運営における課題を解決し、効率的かつ効果的な運営を実現するために、学術大会・国際会議開催システム「アワード」は以下のニーズにお応えします。
-
1. 学会の効率化と人手不足の解消
学会運営では、事務局の業務量が膨大で、少人数で対応するのが難しい場合もあります。学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、煩雑な運営業務を自動化・効率化することで、人的リソースの負担を軽減します。たとえば、参加登録、プログラム作成、講演者管理などがワンストップで完結します。
-
2. 学会運営のコスト削減
学会開催には、印刷物や郵送、事務局人件費など多くのコストが発生します。学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、クラウドベースでの運営によりこれらのコストを大幅に削減可能。さらに、事務局代行費用を削減しつつ、高品質なサービスを提供します。
-
3. 決済機能でスムーズな収益管理
学会参加費や年会費のオンライン決済に対応。安全性の高い決済システムを導入しているため、事務局での入金確認の手間が省け、効率的な資金管理が可能です。これにより、参加者にも事務局にもストレスフリーな学会運営を実現します。
-
4. 学会運営サポートで「大変」を「簡単」に
「学会運営が大変」と感じている学会事務局の方々に向け、運営全般を支援する学会運営サポートをご用意しています。例えば、会場手配、プログラム編成、スポンサー管理など、運営代行サービスもご紹介可能です。
-
5. 柔軟な管理システムで多様なニーズに対応
学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、学会の規模や形式に応じて柔軟にカスタマイズ可能。オンライン学会、ハイブリッド開催にも対応しており、参加者がどこにいても円滑な学会開催をサポートします。
-
6. 費用対効果の高い学会開催を実現
学会開催費用を抑えつつ、質の高い学会運営を目指す方に最適なソリューションです。クラウド型システムの導入で初期費用を抑え、必要に応じて追加オプションを選択することが可能です。
学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、学会の運営をトータルでサポートし、効率化・コスト削減を実現する強力なパートナーです。学会運営の課題を抱える事務局や運営会社の皆さま、ぜひ一度ご相談ください!





