第3回:学会広報の新しい手法~ホームページとSNSの連携更新~【全10回】
2025.11.12
2026.01.16
はじめに
学会広報は、会員との日常的なコミュニケーション、研究成果の社会への発信、新規会員の獲得など、多層的な役割を担っています。近年、情報発信のチャネルは多様化し、ホームページ、Twitter(X)、Facebook、LinkedInなど複数のプラットフォームへの同時対応が求められるようになりました。
学会事務局の現場では、「限られた人員で複数のSNSに対応するのが困難」という声が聞かれます。ホームページ用の記事を書き、それをTwitter用に140字に要約し、Facebook用には別の切り口で書き直すこの繰り返しが、事務局スタッフの大きな負担となっているのが実情です。
ここで注目したいのが、AI技術を活用した広報活動の効率化です。AIは単なる自動化ツールではなく、学術的な専門性を保ちながら、各媒体の特性に合わせた表現への変換を支援してくれる協働パートナーとなり得ます。本記事では、学会広報におけるAI活用の実践的な方法を、具体的な操作例とともにご紹介いたします。
【参考】
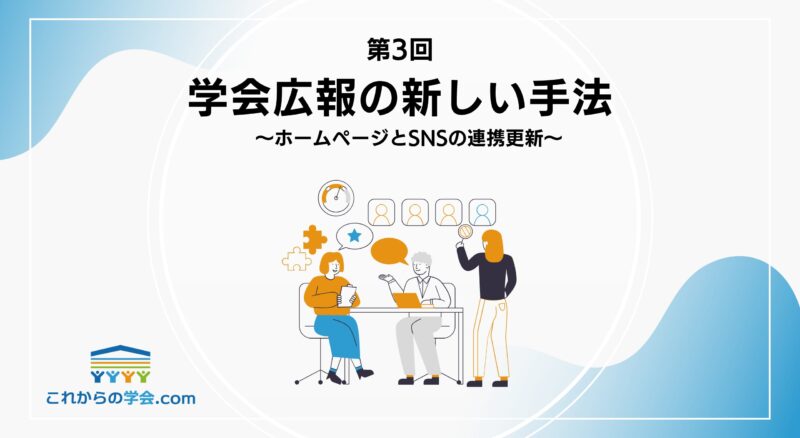
1. AI支援による広報活動の実践
1.1. 学術的内容を踏まえた記事生成と編集支援
学会広報における最大の課題の一つは、学術的な正確性を保ちながら、一般読者にも理解しやすい表現を実現することです。専門用語が並ぶ難解な文章では読まれませんが、かといって専門性を損なうわけにもいきません。
ChatGPTやClaudeといった汎用AIツールは、この課題に対する強力な支援者となります。ただし、最初から完璧を期待するのは禁物です。AI生成文をそのまま使用すると、組織固有のトーンや文脈が失われる可能性があるため、必ず人間による確認と修正が必要です。
学術大会の報告記事を作成する際、以下のようなプロンプト(指示文)を用いることで、バランスの取れた文章の初稿を生成できます。
プロンプト例:
以下の学術大会の情報をもとに、学会ホームページ掲載用の報告記事を800字程度で作成してください。専門用語は必要最小限にとどめ、学会員だけでなく一般の方にも興味を持っていただけるような表現を心がけてください。 【大会情報】 – 日時:2025年9月15日-17日 – 場所:○○大学 – テーマ:「持続可能な社会と△△学の貢献」 – 参加者数:350名 – 基調講演:□□教授による「気候変動と□□研究の最前線」
このような指示により、AIは学術的な内容を一般読者にも親しみやすい形に変換した初稿を提供してくれます。重要なのは、この初稿をそのまま使用するのではなく、専門家の視点で確認・修正を加えることです。AIが生成した文章は「たたき台」として活用し、事務局スタッフや担当委員が最終的な品質管理を行うという役割分担が効果的です。
特化型AIツールとしては、Grammarly(文法・スタイルチェック)やDeepL Write(文章改善提案)なども併用することで、より洗練された文章に仕上げることができます。これらのツールは、文章の明瞭性、簡潔性、一貫性を自動でチェックし、改善提案を提示してくれます。
【参考】
・ChatGPT公式サイト|OpenAI
・Claude公式サイト|Anthropic
・Grammarly – Free Writing AI Assistance|Grammarly
・DeepL Write – AI文章校正・作成ツール|DeepL
1.2. SNSと連動した一括情報発信の仕組み
ホームページに掲載した記事を、TwitterやFacebookなど各SNSに適した形式で展開することは、手作業では非常に時間がかかります。各プラットフォームには文字数制限や推奨される投稿スタイルがあり、同じ内容でも表現方法を変える必要があるためです。
ここでAIの強みが発揮されます。例えば、800字のホームページ記事をもとに、以下のような指示でSNS用の投稿文を生成できます。
操作例:
1. ChatGPTに先ほど作成した記事全文を入力
2. 追加プロンプトを与える:
『この記事をもとに、以下の3つの投稿文を作成してください』
・LinkedIn用:ビジネス専門家向けに400字程度
・Twitter(X)用:140字以内、ハッシュタグ3つ付き
・Facebook用:300字程度、質問形式で締めくくり
このアプローチにより、一つのコンテンツから複数のSNS投稿を数分で準備できます。実際の画面操作では、ChatGPTの対話インターフェースに記事をコピー&ペーストし、上記のような指示を入力するだけです。生成された各投稿案は、それぞれのプラットフォームの特性を考慮した内容になっています。
さらに効率化を図るなら、Buffer や Hootsuite といったSNS管理ツールと組み合わせることも有効です。これらのツールは、複数のSNSアカウントを一元管理し、投稿スケジュールを事前に設定できます。AIで生成した投稿文を各ツールに登録しておけば、最適なタイミングで自動投稿されます。
【参考】
・Buffer – Social Media Management Tools|Buffer ※英文サイトです
・Hootsuite – Social Media Management Platform|Hootsuite ※英文サイトです
1.3. 専門性と親しみやすさの調整方法
学会広報において難しいのは、ターゲット層に応じた「トーンの調整」です。学会員向けの専門的な報告と、一般市民や学生向けの啓発的な情報発信では、同じ内容でも表現方法を変える必要があります。 AIはこの調整作業を支援してくれます。例えば、研究成果の報告記事を異なるトーンで書き分ける場合。
プロンプト例:
以下の研究成果を、3つの異なる読者層向けに書き分けてください。
【原文】(専門的な研究内容の要約)
1.学会員向け(専門用語使用可、厳密な表現)
2.一般市民向け(平易な表現、身近な例示) 3. 高校生・大学生向け(興味を引く表現、学びへの誘導) 各300字程度で。
この方法により、同一の情報を異なる読者層に適切に届けることができます。特に、専門性を損なわずに平易な表現に変換する作業は、人間だけで行うと時間がかかりますが、AIの初稿生成により大幅に効率化できます。
実際の運用では、Notion AIやMicrosoft Copilotなど、業務管理ツールに統合されたAI機能を使うことで、記事の下書きから編集までを一つのプラットフォーム内で完結させることも可能です。
【参考】
・Notion 3.0のご紹介|Notion
・Copilot を使用して組織を強化する|Microsoft
2. 人間とAIの役割分担
2.1. 企画・監修における人間の位置づけ
AI活用において最も重要なのは、「何を伝えるか」という企画段階です。これは明確に人間が担うべき領域です。学会の広報戦略、年間の情報発信計画、各記事のメッセージや目的の設定は、組織の方針や文脈を理解している人間でなければ適切に判断できません。
具体的には、次のような企画・方針決定は人間が行います。
・年間広報計画の策定(どの時期にどのような情報を発信するか)
・重点的に伝えるべきメッセージの選定
・ターゲット読者層の特定と優先順位づけ
・学会としての発信文書のトーン&マナーの維持
また、AIが生成した文章の最終確認と承認も、必ず人間が行うべきです。特に学術的な正確性、倫理的な配慮、組織としての一貫性については、専門家の目による検証が不可欠です。
【参考】
・パブリックリレーションズとは|公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会
2.2. 文章生成・編集におけるAIの強み
一方、AIが真価を発揮するのは、決定された方針に基づく実際の文章生成と編集作業です。AIの強みは以下の点にあります。
速度と量: 人間が1時間かけて作成する記事を、AIは数分で初稿化できます。これにより、事務局スタッフは企画や戦略的な業務により多くの時間を割けます。
一貫性: 過去の投稿スタイルや表現パターンを学習させることで、組織としての文章の統一感を保てます。
多様なバリエーション: 同じ内容を異なる表現で複数パターン生成し、最も適切なものを選択できます。
実務的な活用例として、定期的なイベント告知などの「型が決まっている情報発信」では、テンプレート化したプロンプトを作成しておくと効率的です。
テンプレート例:
【月例セミナー告知テンプレート】
以下の情報をもとに、学会ホームページ用の告知記事を作成してください。
・標題は「○○月度 月例セミナーのご案内」
・構成:日時・場所・演題・講師紹介・参加申込方法
・トーン:丁寧だが硬すぎず、参加を促す表現 – 文字数:500字程度
このようなテンプレートを用意しておけば、毎回変更する部分だけを差し替えるだけで、一定品質の告知記事を素早く作成できます。
【参考】
・プロンプトエンジニアリング入門|Anthropic Claude Documentation ※英文サイトです
2.3. 品質管理を通じた一貫性の確保
AIと人間の協働で最も注意すべきは、品質管理の体制構築です。AI生成文章をそのまま公開することは避け、必ず以下のチェックプロセスを経るべきです。
第一段階:事実確認
- 日時、場所、人名などの固有情報の正確性
- 数値データの検証
- 引用や参考文献の適切性
第二段階:表現チェック
- 学会のトーン&マナーとの整合性
- 専門用語の適切な使用
- 読みやすさと理解しやすさ
第三段階:法的・倫理的確認
- 個人情報保護の観点
- 著作権への配慮
- 差別的・排他的表現の有無
この三段階チェックを効率的に行うため、Googleドキュメントの提案モードや、Microsoft Wordのコメント機能を活用し、複数の担当者が段階的にレビューできる体制を整えることが推奨されます。
AIが生成する文章には、事実誤認や「ハルシネーション」(もっともらしい虚偽情報の生成)のリスクがあることが、複数の研究で指摘されています。そのため、専門家による事実確認は必須のプロセスです。
【参考】
3. 導入における実践的手順
3.1. ChatGPTを用いた記事作成支援
それでは、実際にChatGPTを使った記事作成の具体的な手順を見ていきましょう。ここでは無料版のChatGPTでも実施可能な方法をご紹介します。
ステップ1:背景情報の提供
まず、ChatGPTに学会の基本情報を伝えます。これは一度行っておけば、その会話(スレッド)内では情報が保持されます。
私は○○学会の事務局スタッフです。本学会は△△分野の研究者約500名が所属する学術団体で、年1回の大会と月例セミナーを開催しています。会員の多くは大学研究者ですが、企業研究者や行政関係者も含まれます。広報記事は、専門性を保ちつつも読みやすさを重視した文体でお願いします。
ステップ2:具体的な記事作成依頼
次に、作成したい記事の目的と必要情報を明確に伝えます。
次回の月例セミナーの告知記事を作成してください。
・日時:2025年11月20日(木)18:00-19:30
・形式:オンライン(Zoom)
・演題:「□□技術の最新動向と社会実装への課題」
・講師:◇◇大学 ●●教授 – 対象:会員および関心のある方
・申込:学会ウェブサイトから11月15日まで – 文字数:600字程度
ステップ3:生成結果の確認と修正依頼
生成された記事を確認し、必要に応じて修正を依頼します。
ありがとうございます。ただ、講師紹介の部分をもう少し詳しくし、●●教授の主な研究業績に触れてください。また、「社会実装」という言葉が2回出てくるので、一方を別の表現に変えてください。
このような対話を2〜3回繰り返すことで、求める品質の記事に近づけることができます。重要なのは、一度で完璧を求めるのではなく、段階的に改善していくプロセスです。
ステップ4:複数バージョンの生成
満足のいく記事ができたら、SNS用のバージョンも作成します。
この記事をもとに、Twitter(X)用の投稿文を3パターン作成してください。各140字以内で、適切なハッシュタグを2〜3個つけてください。
このプロセス全体で、慣れれば15〜20分程度で完了します。従来、同様の記事作成に1時間以上かかっていたとすれば、大幅な時間短縮となります。
よくあるトラブルと対処法:
初めてChatGPTを使う方からよく聞かれる質問があります。
・「生成された文章が長すぎる(または短すぎる)
→ 「現在○○字ですが、△△字程度に調整してください」と明確に指示しましょう。
・「専門用語が多すぎる(または少なすぎる)」
→ 「もう少し平易な表現に」「専門的な表現を増やして」と具体的に伝えましょう。
・「同じような表現が繰り返される」
→ 「『〜である』という表現が3回使われているので、別の表現に変えてください」と指摘しましょう。
AIは指示に従順です。遠慮せず、何度でも修正を依頼して構いません。
【参考】
・ChatGPT使い方ガイド|OpenAI Help Center
3.2. SNS管理ツールによる投稿スケジュールの最適化
複数のSNSアカウントを効率的に管理するには、専用の管理ツールの活用が有効です。ここでは無料プランでも使える「Buffer」を例に、実践的な運用方法をご紹介します。
Bufferの基本設定:
1. Bufferのアカウント作成(無料プランで3つのSNSアカウント連携可能)
2. 学会のTwitter、Facebook、LinkedInアカウントを接続
3. 「投稿スケジュール」で各SNSの最適な投稿時間を設定
- Twitter: 平日12:00、18:00
- Facebook: 平日19:00
- LinkedIn: 平日9:00
AIと組み合わせた効率的な運用:
- ChatGPTで各SNS用の投稿文を生成
- 生成された投稿文をBufferの「作成」画面に貼り付け
- 投稿日時を設定(例:次の月曜日12:00)
- プレビューで表示を確認後、スケジュール登録
この方法により、月初めに1ヶ月分の投稿を一括で準備し、スケジュール設定しておくことが可能です。実際の運用では、週に1度程度、予定投稿の内容を見直し、必要に応じて調整を加えます。
投稿効果の分析:
Bufferには分析機能も備わっており、各投稿のエンゲージメント率(いいね、シェア、コメント数)を確認できます。この情報をもとに、どのような内容や投稿時間が効果的かを把握し、次回以降のAI生成プロンプトに反映させることで、継続的な改善が可能となります。
特化型ツールとしては、Hootsuite(より高度な分析機能)、Later(ビジュアル重視のInstagram対応)、Sprout Social(チーム協働機能充実)なども選択肢となります。学会の規模や注力するSNSに応じて、最適なツールを選択してください。
【参考】
・Buffer – Getting Started Guide|Buffer Resources ※英文サイトです
・Hootsuite Services|Hootsuite ※英文サイトです
3.3. 効果測定と改善のサイクル
広報活動におけるAI活用の効果を最大化するには、定期的な効果測定と改善のサイクルを回すことが不可欠です。
測定すべき指標:
- ウェブサイトのアクセス数(Google Analytics)
- SNS投稿のエンゲージメント率(各SNSの分析ツール)
- イベント参加申込数の推移
- 会員からのフィードバック
月次での振り返り手順:
- 前月の主要指標をスプレッドシートに記録
- 特に反応が良かった投稿を分析
- どのような内容が好評だったか
- どの表現スタイルが効果的だったか
- 学んだことをAI活用に反映
- プロンプトの改善
- 投稿スケジュールの調整
- 注力するコンテンツタイプの見直し
この改善サイクルを実践するため、Looker Studio(旧Google Data Studio、無料)などのダッシュボードツールを活用すると、複数のデータソースを統合し、視覚的に把握しやすくなります。Google AnalyticsやSNSのデータを自動的に取り込み、グラフ化することで、月次レポート作成も効率化できます。
さらに進んだ活用として、ChatGPTに過去の投稿データを読み込ませ、傾向分析を依頼することも可能です。
傾向分析を依頼:
過去3ヶ月のTwitter投稿とそのエンゲージメント率のデータです。 (データを貼り付け) このデータから、どのような内容や表現が効果的だったか分析し、今後の投稿戦略の提案をしてください。
このようなデータドリブン(データ主導)なアプローチにより、AI活用の精度は継続的に向上していきます。
【参考】
・ Google Analytics – ウェブ解析とレポート作成ツール
・Looker Studio – データ可視化ツール
まとめ
学会広報におけるAI活用は、情報発信の質と量の両面で大きな可能性を秘めています。ChatGPTやClaudeなどの汎用AIツールを中心に、GrammarlyやBufferといった特化型AIツールを組み合わせることで、限られた人的リソースでも効果的な広報活動を展開できます。
重要なのは、AIを「人間の代替」ではなく「協働パートナー」として位置づけることです。企画・監修・最終確認という人間の専門性が求められる部分と、文章生成・編集・スケジュール管理というAIが効率化できる部分を適切に分担することで、学術的正確性を保ちながら、タイムリーで魅力的な情報発信が実現します。
AI技術は日々進化していますが、その本質的な価値は「人間の創造的な業務により多くの時間を割けるようにする」ことにあります。ぜひ、この記事をサンプルとして小さな一歩から実践を始めてみてください。
【参考】
・我が国の学術情報流通における課題への対応について|文部科学省
←PREV 第2回:学会委員会運営をAIで変える ~AIとの協力で出席確認を丁寧に~
NEXT→ 第4回:会議記録の作成支援~文字起こしから要点整理まで~
学術大会・国際会議開催システム「アワード」のご紹介
学会運営における課題を解決し、効率的かつ効果的な運営を実現するために、学術大会・国際会議開催システム「アワード」は以下のニーズにお応えします。
-
1. 学会の効率化と人手不足の解消
学会運営では、事務局の業務量が膨大で、少人数で対応するのが難しい場合もあります。学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、煩雑な運営業務を自動化・効率化することで、人的リソースの負担を軽減します。たとえば、参加登録、プログラム作成、講演者管理などがワンストップで完結します。
-
2. 学会運営のコスト削減
学会開催には、印刷物や郵送、事務局人件費など多くのコストが発生します。学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、クラウドベースでの運営によりこれらのコストを大幅に削減可能。さらに、事務局代行費用を削減しつつ、高品質なサービスを提供します。
-
3. 決済機能でスムーズな収益管理
学会参加費や年会費のオンライン決済に対応。安全性の高い決済システムを導入しているため、事務局での入金確認の手間が省け、効率的な資金管理が可能です。これにより、参加者にも事務局にもストレスフリーな学会運営を実現します。
-
4. 学会運営サポートで「大変」を「簡単」に
「学会運営が大変」と感じている学会事務局の方々に向け、運営全般を支援する学会運営サポートをご用意しています。例えば、会場手配、プログラム編成、スポンサー管理など、運営代行サービスもご紹介可能です。
-
5. 柔軟な管理システムで多様なニーズに対応
学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、学会の規模や形式に応じて柔軟にカスタマイズ可能。オンライン学会、ハイブリッド開催にも対応しており、参加者がどこにいても円滑な学会開催をサポートします。
-
6. 費用対効果の高い学会開催を実現
学会開催費用を抑えつつ、質の高い学会運営を目指す方に最適なソリューションです。クラウド型システムの導入で初期費用を抑え、必要に応じて追加オプションを選択することが可能です。
学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、学会の運営をトータルでサポートし、効率化・コスト削減を実現する強力なパートナーです。学会運営の課題を抱える事務局や運営会社の皆さま、ぜひ一度ご相談ください!





