第4回:会議記録の作成支援~文字起こしから要点整理まで~【全10回】
2025.11.13
2026.01.16
はじめに 議事録作成に時間がかかりすぎ?
学会事務局の業務のなかでも、委員会や理事会などの議事録作成は、その重要性と労力が両立を求められる中核的な作業です。会議中にリアルタイムでメモを取り、終了後にはその内容を記憶と資料を頼りに整理し、専門用語や固有名詞を正確に記録しなければなりません。
特に学術的な議論では、単なる発言の記録に留まらず、発言の意図や文脈を適切に保存することが求められ、作成者には高度な理解力と表現力が不可欠です。この難易度の高い作業も、AIの補助を組み合わせることで、効率と品質の両立が現実味を帯びます。
AI議事録作成ツールの活用は、議事録作成時間を最大70%短縮できることが実証されており、さらに最新の事例では90%削減を達成したケースも報告されています。事務局担当者の負担を大きく軽減する強力な手段です。近年、音声認識と自然言語処理を組み合わせたAI支援ツールが実用レベルに達し、学会運営の現場でも導入が進んでいます。
本記事では、音声の文字起こしから要点整理、データベース化まで、AIを活用した議事録作成の実践的手法を紹介します。AIによる効率化の恩恵を受けつつも、人間による確認・修正の重要性を踏まえ、議事録の信頼性を高める方法を探ります。
【参考】
・会議革命!AI議事録ツールで議事録作成時間を90%削減する方法【2025年完全版】|not+e(Re-BIRTH株式会社)
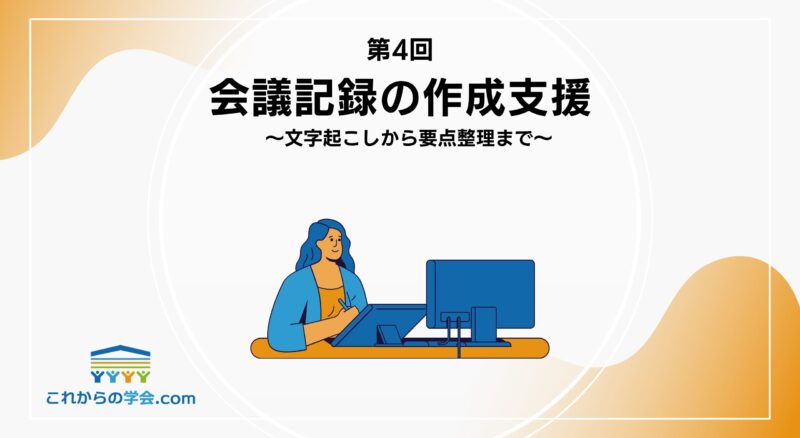
1.AIに手伝ってもらって議事録作りを変える
1.1.音声を文字に変換する技術を使って記録する方法
議事録作成の第一歩は、会議内容を正確に記録することです。AI音声認識技術は、従来の手書きメモや手動入力と比較して、作業効率を飛躍的に向上させます。マイクから入力された音声をAIが解析し、テキストデータに変換するこの技術は急速に発展し、日本語の認識精度も実用レベルに達しています。会議の音声をリアルタイムでテキスト化することで、議事録作成の負担を大幅に軽減できます。
(1)Nottaの実践的活用
Nottaは、日本語に特化したリアルタイム文字起こしツールで、104言語に対応し、日本語の音声認識精度は業界トップクラスとされています。
無料プランでも月間120分の文字起こしが可能で、小規模な学会や月1~2回の会議であれば十分活用できます。より頻繁な会議がある場合は、プレミアムプラン(月額2,000円程度)で月間1,800分まで利用可能です。
実際の操作は、会議前にアプリを起動し、「新規録音」を選択して会議名と日付を入力することから始まります。
参加者全員から録音の同意を得ることは、個人情報保護の観点から必須の手順です。会議中は、発言がリアルタイムでテキスト化され、話者の切り替わりも自動検出されます。
大切な発言箇所には「タグ」機能でマークを付与すれば、後からの確認が容易です。これにより、担当者はメモを取る作業から解放され、議論の内容に集中できる環境が実現します。
会議後の確認作業は、会議時間の30〜40%程度で完了します。生成されたテキストを再生音声と照合しながら確認し、誤認識箇所を修正します。タイムスタンプ付きで保存されるため、該当箇所の音声を確認しながら正確な修正が可能です。特に専門用語や人名の修正は必須です。
(2)その他の高精度な文字起こし技術と個人情報保護
より高精度な文字起こしが必要な場合は、99言語に対応するOpenAIWhisperの活用も選択肢の一つです。また、会議まるごと記録サービスtorunoは、議事録作成の自動化・効率化を支援するクラウドサービスです。
実績や効果に関しては、次のような情報が見つかっています。
・文字起こし時間の削減:実際の利用者の声として、文字起こしにかかる時間が50%削減できたというヒアリング結果があります。
・議事録作成時間全体の短縮:議事録作成時間が59%削減または65%短縮されたという検証記事や体験談が確認されています。
音声録音と文字起こしを行う際は、個人情報保護への配慮が不可欠です。
機密性の高い議題については、
・録音を一時停止する
・生成された文字データは適切に管理し不要になったら削除する
・クラウドサービスを利用する場合はデータの保存場所と管理方針を確認する
以上のようなことが求められます
【参考】
・自動的に音声を文字起こし|Notta
・Whisperが登場|OpenAI
・文字起こし/要約サービスtoruno|リコージャパン
・AI議事録自動作成ツールおすすめ15選!選び方も紹介(無料あり)|ITトレンド
・【続】AIで文字起こしを自動化すると議事録作成の生産性がどのくらい高まるか?|no+e(AYUN著)
1.2.大切な決定事項を自動で見つけ出して分類する手順
文字起こしが完了した数万文字に及ぶテキストから、重要な決定事項や議論のポイントを抽出する作業は、次に大きな労力がかかる工程です。この段階でChatGPTやClaudeなどの汎用AIツールが力を発揮します。
(1)構造化されたプロンプトによる要点抽出
ChatGPT(無料版でも十分に活用可能)を用いた要点抽出では、構造化されたプロンプト(指示文)を入力することで効率的に情報を整理できます。具体的には、文字起こしテキストとともに「決定事項」「継続審議事項」「報告事項」「次回までの宿題」「重要な意見・提案」といった項目に分類して要約するよう指示します。このアプローチにより、ChatGPTは会議内容を構造化して整理し、数秒から数十秒で結果を提示します。
Claudeは長文テキストの処理に優れており、より詳細な分析が可能です。
『この会議で議論された主要な論点を3つ挙げ、それぞれについて賛成意見と反対意見をまとめてください』
といった高度な指示に対応できます。発言者ごとの意見の整理、賛成・反対意見の対比、議論の論点抽出、未解決課題の明確化などを構造化された分析結果として得られます。
(2)ツールの使い分けと継続事項の追跡
迅速な要約にはChatGPT、詳細な分析にはClaudeと、目的に応じてツールを使い分けることが効果的です。
両方を併用する場合は、ChatGPTで初期要約を作成し、Claudeで詳細分析を行い、最後に人間が最終確認するという流れが推奨されます。
また、過去の議事録テキストとともに「次期大会準備に関する決定事項をすべて抽出し、時系列で整理してください」といった指示を出すことで、継続審議事項の進捗状況を一覧化でき、議論の連続性を保ちながら効率的な議事録作成が可能となります。NotionAIの要約機能も、議事録を一元管理しながら利用できる利点があります。
【参考】
・あなたのニーズを叶えるAIワークスペース。|Notion
・Claude(クロード)日本語無料版|aiclaude.jp
1.3.過去の議事録との関連性を分析して継続性を保つ工夫
学会運営において、議論の継続性を保ち、組織としての一貫性を維持することは不可欠です。過去の決定事項や議論との整合性を確認する仕組みが必要です。
(1)Notionを活用した議事録データベースの構築
Notionは、議事録データベースを構築し、過去の記録との関連性を分析する機能を提供します。基本的なデータベース機能は無料プランでも使用できますが、AI機能(要約、関連ページ検索など)は有料プランで利用可能です。
データベース構築の第一段階では、Notionで「議事録データベース」を作成し、日付、会議名、参加者、決定事項などのプロパティを設定します。各議事録をページとして登録することで、構造化された情報管理が可能となります。
NotionAIの有料機能を活用すれば、「前回の理事会で議論された予算案との関連を説明してください」といった質問により、過去の議事録から関連情報を自動抽出できます。無料プランで運用する場合でも、タグ付けやカテゴリ分類によりテーマ別に議事録を整理し、全文検索機能(無料)によりキーワードから瞬時に該当箇所を発見できます。また、リンク機能で関連する議事録同士を相互参照することで、議論の流れを追跡可能です。
無料プランでの代替案と組織記憶の継承
NotionAIの有料機能を使わない代替案として、GoogleドキュメントとChatGPTの組み合わせも有効です。議事録をGoogleドキュメントで管理し、過去の議事録をChatGPTに読み込ませて関連性を分析できます。スプレッドシートでのタグ管理により、議事録の要約を一覧化し、フィルタ機能で関連議事録を抽出する方法も実用的です。
| 項目 | Notion(基本機能) | NotionAI(追加機能) |
| 役割 | ワークスペース、データ管理、文書作成のプラットフォーム。 | 生成AIアシスタント。文章の作成、要約、翻訳、アイデア出しなどの作業を自動化。 |
| 技術 | データベース、ページ構造、リンク、共有など。 | 大規模言語モデル(LLM)に基づく自然言語処理。 |
| 料金 | 無料プランあり(個人利用向け)。チーム利用は有料。 | 基本的に有料のアドオン。基本プランに追加して契約が必要。 |
| できること | 議事録の保存、データベース構築、タスク管理、情報整理、テンプレート作成。 | 議事録の自動要約、決定事項の抽出、長文の言い換え、過去データに基づく質問への回答。 |
【参考】
・共同編集が可能なオンラインのドキュメント|GoogleWorkspace
・コンテンツの共同作業と共有を安全に|MicrosoftSharePoint
2.学術的な議論を記録する時に気をつけること
2.1.人間が内容を確認・修正することの大切さ
AI技術の精度が向上しても、議事録作成における人間の役割は依然として不可欠です。「AIは支援ツール、最終判断は人間」という原則が議事録作成でも大事です。
AIは発言の表面的な意味は理解できますが、発言者の真意や会議の文脈、微妙なニュアンスを完全に把握することには限界があります。この微妙なニュアンスの理解には人間の判断が不可欠です。
実際の確認プロセスでは、まずAI生成の要約を読み、会議の全体的な流れと整合しているか確認します。次に重要な決定事項について、発言者の意図が正確に反映されているか検証します。曖昧な表現や誤解を招く可能性のある記述を修正し、必要に応じて会議参加者に確認を依頼します。議事録は法的・制度的にも大切な文書であり、最終的な責任は人間が負うべきものです。AI支援により作成効率は向上しますが、内容の正確性について最終確認を行うのは人間の責務です。
2.2.専門用語や固有名詞を正確に記録する方法
学会における議論では、専門用語や研究者名、機関名などの固有名詞が頻繁に登場し、これらの正確な記録は議事録の信頼性に直結します。
Nottaなどの音声認識ツールでは、カスタム語彙を登録することで、学会固有の用語への認識精度が大幅に向上します。登録すべき用語には、学会特有の専門用語、研究者名、機関名、プロジェクト名などが含まれます。
専門用語の正確性を担保するため、確認ワークフローの確立が肝心です。AI文字起こし直後に専門用語リストを作成し、学会の専門委員または当該分野の研究者に用語確認を依頼します。修正版を作成して最終版として保存し、確認された用語をカスタム辞書に追加することで、次回以降の精度向上につなげます。ChatGPTを活用し、誤変換の可能性がある用語を指摘させることも有効です。
2.3.議論の流れや意図を適切に保存する手順
学術的な議論では、結論だけでなく、そこに至るプロセスも外せない記録対象です。議論の構造を可視化することで、後から議事録を読む人が議論の経緯を理解しやすくなります。
ChatGPTに「議論の流れを図式化してください」という指示とともに、提起された問題、提案された解決策、賛否意見、最終的な決定といった項目を指定することで、議論構造を明確化できます。マークダウン形式で階層構造を表現するよう指示すれば、読みやすい形式での出力が得られます。
特に大切な発言については、要約ではなく原文を引用形式で保存することが推奨されます。Claudeに重要と思われる発言を自動抽出させ、引用箇所については必ず人間が確認し、文脈上適切かどうかを判断する必要があります。また、「前回会議で決定された方針」といった表現により、過去の議事録との関連性を明示することで、議論の継続性を保つことができます。
3.実際にツールを導入して運用管理する方法
3.1.Nottaを使った音声録音・文字変換の仕組み
学会事務局でNottaを導入する際は、アカウント設定→初回テスト→本格運用の段階的なアプローチが効果的です。
アカウント設定後、小規模な打ち合わせで試験的に使用し、録音品質と認識精度を確認します。本格運用では、委員会・理事会での正式採用を決定し、参加者に録音について事前に説明して同意を得ます。定期的にカスタム語彙を更新し、継続的な改善を図ります。
会議後のテキスト編集モードでは、誤認識箇所を直接修正でき、音声再生と同期しているため正確な修正が可能です。
運用上の留意点として、音声品質の確保(ノイズの最小化)や、プライバシー配慮(機密性の高い議題での録音一時停止)が不可欠です。また、重要な会議では、AI文字起こしに加え、従来の手動メモも併用するなど、バックアップ体制を整えることが推奨されます。
【参考】
3.2.AIで要点を抜き出して整理する方法
文字起こし後の要点整理プロセスでは、ChatGPTとClaudeを使い分ける戦略が効果的です。
ChatGPTは、迅速な概要把握や決定事項の箇条書きリスト作成、複数議事録の統合分析に適しています。Claudeは、長文処理や複雑な論点整理、詳細な議論分析に向いています。
AI生成の要約を最終版とする前に、品質管理のチェックを実施します。決定事項の漏れ、発言者の意図の正確性、専門用語の誤り、議論の文脈、継続事項の明確さなどを確認します。このチェックリストに基づき、人間による最終確認と修正を行うことで、議事録の信頼性が確保されます。
3.3.検索できる議事録データベースの作り方
長期的な組織記憶の構築には、検索可能な議事録データベースが不可欠です。Notionを活用したデータベース構築は、組織的知識管理の基盤となります。
データベース構造の設定では、会議名、開催日、参加者、主要テーマ、決定事項といったプロパティを設定します。議事録の標準フォーマットをテンプレート化することで、記録の一貫性を確保します。
検索性能を最適化するため、主要カテゴリ、年度、状態などのタグ付けルールを確立します。これにより、複合条件での検索が瞬時に可能になります。機密性の高い議事録については、Notionのアクセス権限機能を活用し、段階的なアクセス制御により情報セキュリティと透明性のバランスを実現します。
まとめ 議事録の信頼性を担保するのは人間
本記事では、AIを活用した議事録作成の実践的手法を、音声文字起こしから要点整理、データベース構築まで包括的に見て来ました。
NottaやOpenAIWhisperによる音声文字起こしは、議事録作成の初期工程を劇的に効率化し、ChatGPTとClaudeを用いた要点抽出により、重要情報が構造化されます。最新の事例では、120分の会議の議事録作成が12分に短縮され、90%の削減を達成しています。
Notionなどを活用したデータベース構築は、組織記憶の基盤となり、学会運営の継続性と一貫性を強化します。
AIは強力な支援ツールです。
しかし、学術的議論の本質的な価値や文脈を理解し、責任を持って記録するのは人間の役割です。人間による確認・修正を組み合わせることで、議事録の信頼性が担保されます。
【参考】
・会議革命!AI議事録ツールで議事録作成時間を90%削減する方法【2025年完全版】|note(Re-BIRTH株式会社)
よくあるご質問(FAQ)
ここでは、会議の発言録・議事録作成に関するツールの機能について、よくあるご質問にお答えします。
Q1.会議の発言中の「え〜と〜」とか「その〜」などの場繋ぎ言葉を削除して発言録を作ることはできますか?
A1.可能です。
多くの発言録・議事録作成ツールには、「フィラー」と呼ばれるこれらの場繋ぎ言葉を自動で認識し、文字起こし結果から削除する機能が搭載されています。
「えーと」「あのー」「そのー」といった言葉は、話し言葉では自然ですが、文章化すると冗長に感じられるため、議事録や発言録を作成する際に自動で除外できると、編集の手間が大幅に減り、より読みやすいテキストが得られます。
Q2.ノイズフィルター機能として、会議室外の騒音(例えば救急車のサイレン音)などは除外できますか?
A2.部分的には可能ですが、完全に除外することは難しい場合があります。
多くのツールのノイズリダクション機能は、エアコンの動作音やキーボードのタイピング音などの定常的な環境ノイズや、ハウリングなどを抑制するのに効果を発揮します。しかし、救急車のサイレン音のような突発的で音量変化の激しい外部音や、人の話し声に近い周波数帯のノイズについては、音声認識の精度を保ちながら完全に除去するのは技術的に困難です。
重要なのは、録音環境を整えることです。なるべく静かな場所で録音し、参加者の声がクリアに拾えるように、適切なマイクの配置や設定を行うことが、最も効果的な対策となります。
Q3.予め議事録フォーマットが決まっている書式に、会議内容を落とし込むことは可能ですか?
A3.ツールによって機能の提供状況は異なりますが、可能です。
多くの議事録作成ツールでは、あらかじめ設定したテンプレートに、文字起こしされた会議内容を自動で挿入・整形する機能を提供しています。
例えば、「会議名」「日時」「参加者」「決定事項」「ToDo」などの項目を定型化しておき、AIが抽出した要約や決定事項などを、指定のフォーマットの該当箇所に自動で反映させる仕組みです。これにより、文字起こしされたrawデータから、体裁の整った最終的な議事録へと仕上げる時間を大幅に短縮できます。ツールの設定やカスタマイズの自由度を確認してみてください。
【参考】ツール選びのポイント
| 検討事項 | 概要 |
| フィラーの自動削除機能 | 発言録の可読性向上に直結します。 |
| ノイズリダクションの性能 | 特に外部騒音の多い環境での利用を想定する場合に重要です。 |
| テンプレート・フォーマット機能 | 決まった書式での議事録作成が必須な場合に効率化できます。 |
| セキュリティ機能 | 機密性の高い情報を扱う場合は必須です。 |
| AI議事録ツール名 | Q1.フィラー(場繋ぎ言葉)の削除機能 | Q2.ノイズフィルター・リダクション機能 | Q3.議事録テンプレート・フォーマット機能 |
| スマート書記 | 搭載(フィラー除去機能) | 搭載(雑音の自動除去) | 搭載(自社フォーマット対応可能) |
| ZMEETING | 搭載(フィラー除去機能) | 搭載(高精度なノイズリダクション) | 搭載(多様な出力形式に対応) |
| Notta | 搭載(フィラー除去機能) | 搭載(高精度なノイズ除去) | 搭載(要約・タスク抽出も可能) |
| RimoVoice | 搭載(ケバ取り機能) | 搭載(音声認識技術でノイズ抑制) | 搭載(要約機能と連携) |
| AIGIJIROKU | 搭載(フィラー・雑音除去) | 搭載(雑音除去) | 搭載(決定事項やタスクの自動整理) |
| toruno | 搭載(フィラー除去機能) | 搭載(ノイズ低減機能) | 搭載(要約・アクションアイテム抽出) |
| PlaudNote(デバイス連携)※ | ツール連携で可能 | 搭載(専用デバイスで全方位収音+ノイズ低減マイク) | 搭載(要約・タスク抽出機能と連携) |
【注記】
- Q1のソリューションは、編集作業で俗に言われる「ケバ取り」作業をAIが代行する機能です。
- Q2については、技術的な限界があることを明記し、環境整備が重要という現実的なソリューションを強調しました。
- Q3は、ただ文字起こしをするだけでなく、最終的な文書作成の工程までAIがサポートする機能であることを示しています。
※Plaud Note AIボイスレコーダー
https://jp.plaud.ai/products/plaud-note-ai-voice-recorder
【参考】
・学会運営の新たな常識:zoom 会場のマイク設定が成功の鍵を握る|これからの学会.com
←PREV 第3回:学会広報の新しい手法~ホームページとSNSの連携更新~
NEXT→ 第5回:論文関連業務の負担軽減~作成支援から査読管理まで、事務局を支えるAI活用~
学術大会・国際会議開催システム「アワード」のご紹介
学会運営における課題を解決し、効率的かつ効果的な運営を実現するために、学術大会・国際会議開催システム「アワード」は以下のニーズにお応えします。
-
1. 学会の効率化と人手不足の解消
学会運営では、事務局の業務量が膨大で、少人数で対応するのが難しい場合もあります。学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、煩雑な運営業務を自動化・効率化することで、人的リソースの負担を軽減します。たとえば、参加登録、プログラム作成、講演者管理などがワンストップで完結します。
-
2. 学会運営のコスト削減
学会開催には、印刷物や郵送、事務局人件費など多くのコストが発生します。学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、クラウドベースでの運営によりこれらのコストを大幅に削減可能。さらに、事務局代行費用を削減しつつ、高品質なサービスを提供します。
-
3. 決済機能でスムーズな収益管理
学会参加費や年会費のオンライン決済に対応。安全性の高い決済システムを導入しているため、事務局での入金確認の手間が省け、効率的な資金管理が可能です。これにより、参加者にも事務局にもストレスフリーな学会運営を実現します。
-
4. 学会運営サポートで「大変」を「簡単」に
「学会運営が大変」と感じている学会事務局の方々に向け、運営全般を支援する学会運営サポートをご用意しています。例えば、会場手配、プログラム編成、スポンサー管理など、運営代行サービスもご紹介可能です。
-
5. 柔軟な管理システムで多様なニーズに対応
学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、学会の規模や形式に応じて柔軟にカスタマイズ可能。オンライン学会、ハイブリッド開催にも対応しており、参加者がどこにいても円滑な学会開催をサポートします。
-
6. 費用対効果の高い学会開催を実現
学会開催費用を抑えつつ、質の高い学会運営を目指す方に最適なソリューションです。クラウド型システムの導入で初期費用を抑え、必要に応じて追加オプションを選択することが可能です。
学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、学会の運営をトータルでサポートし、効率化・コスト削減を実現する強力なパートナーです。学会運営の課題を抱える事務局や運営会社の皆さま、ぜひ一度ご相談ください!





