第5回:論文関連業務の負担軽減~作成支援から査読管理まで、事務局を支えるAI活用~【全10回】
2025.11.14
2026.01.16
はじめに 研究成果の発表を支える事務局業務
学会事務局における論文関連業務は、多くの場合、投稿者に大きな負担をかけています。特に抄録作成の段階では、著者が何度も修正を繰り返し、事務局はそれに応じて査読システムでの管理、修正版の受領確認、不備への催促などに追われるのが実情です。
第4回「会議記録の作成支援」では、AI音声認識と自然言語処理により議事録作成時間を最大90%削減できることを紹介しました。同様に、論文・抄録作成業務においても、AIの活用により投稿者と事務局双方の負担を大幅に軽減できます。
本記事では、研究発表に伴う抄録作成の効率化から、複数投稿の品質管理、英語表現の改善までを支援するAI活用の実践的手法を解説します。重要なのは、AIを「査読の代替」ではなく、「著者と事務局のサポートツール」として位置づけることです。
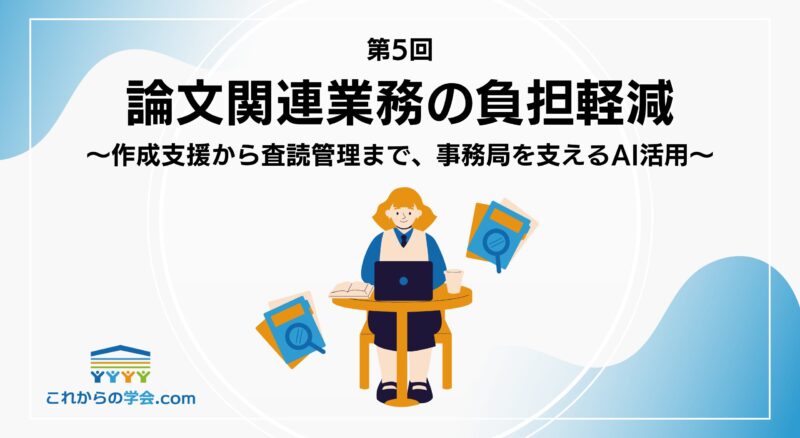
1. AIを活用した抄録作成の実践方法
1.1. キーワード入力から構成案を得る手法
学会への投稿では、「背景」「目的」「方法」「結果」「結論」という標準的な構成が求められることがほとんどです。けれども、この標準的な型に情報を落とし込む作業が、意外と時間を取られるものです。特に複数の研究成果を発表する場合、抄録作成に数時間以上費やすことになりかねません。
ここで有効なのが、ChatGPTやClaudeといった汎用AIツールです。キーワードと基本情報を入力するだけで、構成に沿った初稿を数分で生成できます。
【実践例】ChatGPTによる抄録初稿生成
ステップ1:投稿者に入力フォームを提供
投稿者向けの入力フォームを以下のように準備します。
【学会抄録作成支援フォーム】
・研究テーマ
・研究の背景(現状の課題など)
・研究の目的
・研究方法(実験方法、調査方法など)
・得られた主要な結果(数値データ)
・結論として主張したいこと
・参考キーワード3~5個
ステップ2:ChatGPTに構成案を生成させる
投稿者が記入したデータを、ChatGPTに以下のプロンプトで入力します。
学会投稿用の抄録を作成してください。以下の情報を「背景」「目的」「方法」「結果」「結論」の5項目に構成し、合計400字程度でまとめてください。著者の専門分野の読者にも、学際的な研究者にも理解しやすい表現を心がけてください。
【入力情報】
・研究テーマ:[テーマ]
・背景:[背景情報]
・目的:[目的]
・方法:[方法]
・結果:[結果]
・キーワード:[キーワード]
ステップ3:生成結果を著者に提供
ChatGPTの出力をWordやGoogleドキュメントでテンプレート化し、著者に返します。著者はこの初稿を確認し、細部を修正する方式に変わります。
従来の方法(著者がゼロから執筆)では、複雑な研究内容の抄録作成に2~3時間程度かかかります。
一方、AI生成初稿を改定する方式では、確認・修正時間のみで30~45分程度に短縮できます。これは投稿締め切り直前の著者負担を大幅に軽減し、より質の高い抄録を実現する可能性をもたらします。
1.2. 学術的表現を整えるための調整策
AI生成の初稿は、構成としては適切でも、表現の精密さや学術的な厳密性の点で改善が必要な場合があります。ここで活躍するのが、Grammarly や DeepL Write といった特化型AIツールです。
【実践例】Grammarlyによる学術表現の改善
Grammarlyは、単なる文法チェックにとどまらず、表現の明確性、学術的なトーン、冗長表現の指摘を行います。日本語で作成した抄録を改善する場合、以下の手順が有効です。
ステップ1:初稿をWord/Googleドキュメントに貼り付け
ChatGPTで生成された初稿をコピーし、Grammarlyが統合されたWordやGoogleドキュメントに貼り付けます。
ステップ2:「アカデミック」設定を選択
Grammarlyの設定で「トーン」を「フォーマル/アカデミック」に設定し、学術的な表現を求めます。提案されたスタイルの改善を確認し、受け入れるか拒否するかを選択します。
ステップ3:冗長表現の削除
Grammarlyが指摘した冗長な表現(「〜である」が3回繰り返されているなど)を修正し、簡潔で読みやすい表現に整えます。
さらに詳細な語彙の改善には、特化型ツールのDeepL Writeも有用です。DeepL Write では、文の改善提案が日本語でも提供され、より自然な学術表現への修正が可能です。
1.3. 多言語対応による国際的発信力の強化
学会によっては、英語でのabstract投稿を求めるもの、あるいは日本語抄録と英語アブストラクト(abstract)の両方の提出が必要な場合があります。英語表現の品質向上は、国際的な研究成果の発信において最も重要な鍵となります。
抄録とAbstractの違いまとめ
| 項目 | 抄録(しょうろく) | Abstract(アブストラクト) |
| 言語 | 主に日本語 | 主に英語 |
| 使用場面 | 国内学会、研究報告書、行政文書など | 国際学会、英語論文、海外ジャーナルなど |
| 目的 | 本文への導入・背景説明・研究意義の提示 | 研究の全体像(目的・方法・結果・結論)の要約 |
| 構成の傾向 | 背景や課題意識が中心、本文への誘導を意識 | IMRaD構成(Introduction, Methods, Results, Discussion)を簡潔に反映 |
| 文字数の目安 | 約400~800字(日本語) | 約150~300語(英語) |
| 読者層 | 日本語話者、国内研究者 | 英語話者、国際的な研究者 |
| SEO・検索性 | 国内データベース中心 | 国際データベース(PubMed, Scopusなど)に対応 |
ChatGPT や Claude のような汎用AIツールに加えて、DeepL や Google Translate を活用することで、高品質な英訳が実現できます。
【実践例】多言語抄録の作成フロー
ステップ1:日本語抄録をClaudeに入力
日本語で作成した抄録を、Claudeに以下のように指示します。
以下の日本語学会抄録を英語に翻訳してください。
医学/科学分野の学会投稿用であり、形式的で正確な表現が必要です。
英語ネイティブの査読者にも理解しやすい表現を心がけてください。
【日本語抄録】
[日本語テキスト]
ステップ2:DeepL Writeで表現を洗練
Claudeの英訳をDeepL Writeにコピーし、より自然な英語表現への改善を依頼します。DeepL Writeは科学論文の英語改善に特化した機能を備えており、academic tone の改善が可能です。
ステップ3:ChatGPTで最終確認
生成された英文をChatGPTに入力し、『この英語抄録は国際学会投稿レベルの品質ですか?改善点があれば指摘してください』と確認します。
この多言語対応により、投稿者は英語表現に関する不安を大幅に軽減でき、事務局も英語品質のばらつきを統制できます。
【参考】
・学会発表の準備が変わる!生成AIで抄録作成を効率化する魔法のプロンプト|Noah Shin
・ChatGPTで論文を正確&短時間要約するプロンプト術!テンプレ・失敗改善まで|AI経営総合研究所
2. AI導入で解決!従来の抄録作成における4つの課題
2.1. 著者間での品質のばらつき
学会に投稿される抄録の品質は、著者の執筆経験や言語スキルに大きく左右されます。初めて学会発表する若手研究者と、経験豊富な研究者では、明らかに構成と表現の質に差が生じます。
事務局が高い品質基準を設定しても、著者が基準を理解できず、何度も修正が必要になるケースが多々あります。これは著者側の負担だけでなく、事務局の査読・指導業務の効率を著しく低下させます。
2.2. 締切直前に集中する負担
締め切りが近づくにつれ、著者から修正版が次々と届きます。事務局は、「この表現は学術的に適切か」「背景説明は十分か」などの確認を個別に行わなければなりません。
複数の投稿が重なる場合、事務局スタッフは数日間、抄録の確認・指導に専念することになり、他の業務がおろそかになりかねません。締め切り前の焦りと緊張は夏休み最終週のような慌ただしい状況になります。これは原稿の正確なチェックと投稿者への丁寧なフィードバックの妨げとなります。
2.3. 英語(外国語)表現に関する負担と不安
日本語での抄録作成は何とか対応できても、英語abstractの作成には著者も事務局も不安を感じます。特に、「研究成果の質は高いが、英語表現が稚拙である」ために、国際学会での採択が見送られる事例も報告されています。
2.4. 抄録品質を確保するためのチェックリスト
AIを活用して抄録を作成する際、事務局が確認すべき品質管理ポイントを体系化することが重要です。以下のチェックリストを用いることで、投稿品質の一貫性を確保し、査読委員への負担を軽減できます。
| 確認項目 | 確認内容 | AI活用ツール | 確認者 |
| 構成の完全性 | 「背景」「目的」「方法」「結果」「結論」の5項目がすべて記載されているか | ChatGPT(構成チェック)、Claude(論理性検証) | 事務局 |
| 字数準拠 | 投稿ガイドの字数制限(通常300~500字)に準拠しているか | Word/Googleドキュメント(字数カウント) | 事務局 |
| 学術的表現 | 用語が正確で、専門分野の読者に理解可能か。曖昧表現がないか | Grammarly(表現チェック)、Claude(専門用語検証) | 事務局/ 査読委員 |
| 英文品質 | 英語abstractがある場合、文法・表現が学術レベルか | DeepL Write、ChatGPT(英文チェック) | 事務局/ 英語対応者 |
| データの正確性 | 数値、実験方法、結論が研究内容と合致しているか | 人間による事実確認(AIでは検証不可) | 査読委員/著者 |
| 独創性・新規性 | 既存研究との比較で、学会への投稿価値があるか | Claude(文献背景の分析) | 査読委員 |
| 倫理的配慮 | 被験者への配慮、情報セキュリティ、利益相反の記載がるか | ChatGPT(倫理項目チェック) | 倫理委員会/事務局 |
このチェックリストに基づき、投稿後・査読前の段階で事務局が初期品質確認を実施すれば、明らかに投稿ガイドに合わないものを早期に発見でき、著者への修正指示がより効率的になります。
特に、「AI活用ツール」を参考に、必要なツールを段階的に導入することで、小規模な学会から大規模な学会まで、柔軟に対応することが可能です。
【参考】
・Grammarly – Free Writing AI Assistance|Grammarly
・DeepL Write:AI文章校正・作成ツール|DeepL
3. 実務に即したAI活用手順
3.1. ChatGPTを用いた初稿生成の実例
学会事務局がAIを導入する際の実装手順を、段階的に説明します。
第1週:投稿者向けフォームとプロンプトの準備
- 学会投稿ガイドラインを分析(字数制限、構成要件など)
- 投稿者向けの入力フォームを作成
- ChatGPTの学会抄録用プロンプトテンプレートを作成
第2週:試験運用
- 若干名の投稿者にテスト運用を依頼
- 生成初稿の品質を確認し、プロンプトを改善
- 投稿者からのフィードバックを収集
第3週以降:本格運用
- 投稿受付時に、投稿者に「抄録作成支援フォーム」と利用ガイドを提供
- 著者がChatGPTで初稿を生成(またはAIサポート窓口で事務局が生成)
- 事務局が学会基準に基づき品質確認
- 不備があれば、具体的な修正指示を著者に返却
実施に要する時間の目安:
従来の方法:1件の抄録確認に20~30分(複数の修正往来を含む)
AI活用後:初稿確認10分 + 修正確認5分 = 15分程度 (事務局の負担は約50%削減、著者の執筆時間は約70%削減)
3.2. Grammarlyによる文法確認のプロセス
Grammarlyの導入により、学術的な表現の質を組織的に統制できます。
【実装手順】
ステップ1:事務局スタッフ向けのGrammarly設定
- 学会事務局用のGoogleワークスペースアカウントを設定
- GrammarlyをGoogleドキュメントに統合
- 「学術的トーン」「フォーマル」を既定設定に
ステップ2:著者への提供方法
- 著者から投稿されたWord/Googleドキュメントの抄録を受け取る
- 事務局がGrammarlyで確認し、推奨修正を赤字で表示
- 著者に修正版を返却(修正理由の簡単な説明付き)
ステップ3:反復的な品質向上
- 著者が修正を受け入れ、再投稿
- 事務局で最終確認
- 学会基準に合格した版を受理
Grammarlyの効果:
- 表現の重複排除:冗長な表現を自動指摘
- 学術的トーンの統一:全投稿の表現スタイルが一貫性を持つ
- 執筆時間の短縮:著者が自分で修正提案を確認できるため事務局の指導時間が削減
3.3. AIツール比較表
論文抄録作成支援に使用されるAIツールは多様です。学会事務局が導入するツール選定時の参考として、主要なツールを比較表にまとめました。
| ツール名 | 用途 | 料金 | 日本語対応 | 特徴 | 推奨用途 |
| ChatGPT(OpenAI) | 抄録初稿生成、質問応答 | 基本無料※(Plus/Pro/Business は有料) | ◯ | 汎用性が高く、プロンプト工夫で多様な対応が可能。無料版でも十分利用可能 | 初稿作成(研究テーマから構成を新規作成)、既存案の改善(著者が下書きした初稿を改善) |
| Claude(Anthropic) | 詳細分析、複雑な論点整理 | 基本無料※(有料プランあり) | ◯ | 長文処理に優れ、詳細な分析が可能。複雑な研究内容の整理に適す | 詳細分析、論理性検証 |
| Grammarly | 学術表現改善、文法チェック | フリープラン有(プレミアムは月額12ドル) | ◯ (日本語は限定的) | アカデミック設定で学術的トーンに自動調整。リアルタイム修正提案 | 日本語抄録の表現改善 |
| DeepL Write | 多言語翻訳、英文改善 | 無料版あり(有料プランあり) | ◯ | 自然な翻訳と英文改善に特化。学術表現の改善提案が豊富 | 英語抄録作成、翻訳 |
| Gemini | 抄録作成補助、質問応答 | 基本無料 | ◯ | ChatGPTと同等の性能。Googleツールとの連携が容易 | 既存案の改善(著者が下書きした初稿を改善) |
| Notion AI | テンプレート管理、要約 | 有料プランのみ | ◯ | テンプレート化された抄録管理に適す。データベース機能と連携 | 複数投稿の一元管理 |
※2025年10月時点。料金体系は変動する可能性があります。学会の規模や投稿件数に応じて、最適なツールを選定してください。
3.4. 複数AIを組み合わせた品質向上の流れ
最高の効率と品質を実現するには、複数のAIツールを統合的に活用する必要があります。
【統合的な活用フロー】
①初稿生成:ChatGPT
投稿者または事務局が、ChatGPTで抄録初稿を生成
②評価:Claude
Claudeに初稿を入力し、『この抄録の強みと弱みを分析してください。特に学術的な厳密性と文章の明確さについて』と指示 結果から改善点を抽出
③表現改善:DeepL Write + Grammarly
修正内容をDeepL Writeで自然な表現に変換 Grammarlyで学術的なトーンに統一
④最終確認:人間による査読
⑤事務局または査読委員が最終的な学術的価値と投稿ガイド準拠を確認
⑥採択またはリジェクト
この流れにより、投稿から採択判断まで、投稿者と事務局双方が最小限の負担で、高品質の審査プロセスを実現できます。
【参考】
・ChatGPT公式サイト|OpenAI
・Claude公式サイト|Anthropic
まとめ 研究者と事務局を支えるAIとの協働
学会における論文関連業務のAI活用は、単なる時間短縮ではなく、研究成果の質的向上と学会運営の透明性強化を実現するための手段です。ChatGPTによる初稿生成、Grammarlyによる表現改善、DeepL Writeによる多言語対応を統合することで、次の効果が期待できます。
投稿者側のメリット
・抄録作成時間を70%削減
・英語表現(外国語表現)への不安を軽減
・学術的な構成の規範を学べる
事務局側のメリット
・査読・指導時間を50%削減
・投稿品質のばらつきを統制 ・対応ミスを防止
学会全体のメリット
・高品質な論文投稿を促進
・査読負担を軽減
・国際学会での採択率向上
重要なのは、AIを「査読者の代替」ではなく、「著者・事務局・査読者を支援するパートナー」として位置づけることです。最終的な学術的価値の判断は人間の専門家に委ね、AIは執筆効率と表現品質の向上に専念するという役割分担が、持続可能で倫理的なAI活用を実現します。
ここで紹介した方法は、学会の規模や投稿件数に応じてカスタマイズ可能です。まずは試験運用から始め、投稿者と事務局の実感に基づいて改善を重ねることが肝心です。
【参考】
・【2025】要約ができるAIツールおすすめ14選!カテゴリ別・注意点やコツも解説|スマート書記
・生成AIを受容・活用する社会の実現に向けて令和7年(2025年)2月27日|日本学術会議
よくあるご質問(FAQ)
Q1. ChatGPTで生成した抄録をそのまま投稿しても大丈夫ですか?
A1. 残念ながら、そのままの投稿は推奨しません。
AI生成の抄録には、以下のリスクがあります:
- 事実誤認:AIが「もっともらしい虚偽情報」を生成する「ハルシネーション」が発生する可能性があります。特に数値データ、研究方法、参考文献については、必ず著者本人による確認が必須です。
- 学術的不正:AI生成文を著者の成果として投稿することは、学術倫理に抵触する可能性があります。学会によっては「AI使用の明記」を求める投稿規定もあります。
- 学術的価値の損失:AIは統計的に最もあり得そうな表現を生成するため、研究の独創的側面が失われる可能性があります。
- 推奨される使用方法: AIは「執筆の補助ツール」として使用し、最終的な学術的責任は著者が負うべきです。生成初稿を確認・修正してから投稿してください。
Q2. 英語が苦手な著者でも、良質な英文abstractを作成できますか?
A2. はい、可能です。
Claude + DeepL Writeの組み合わせにより、実務的な英文品質を達成できます。
手順:
- 著者が日本語抄録を作成
- Claudeに日本語を英語に翻訳するよう指示(医学用語や学術表現を厳密に)
- DeepL Writeで英文の自然さを改善
- ChatGPTに『この英文は学術レベルですか?』と確認
- 事務局または英語対応者が最終確認
このプロセスにより、英語表現に関する不安を大幅に軽減できます。ただし、著者が研究内容の正確性を最終確認することは不可欠です。
Q3. 学会によって投稿規定が異なりますが、AIで対応できますか?
A3. 対応可能ですが、工夫が必要です。
学会により、抄録の構成(「背景」「目的」の統合など)、字数制限、必須項目が異なります。このため、ChatGPTのプロンプトに学会固有の規定を明記することが重要です。
例:以下の学会投稿規定に従い、抄録を作成してください。
【投稿規定】
・字数:350字以内
・構成:「背景と目的」「方法」「結果」「考察」
(「背景」と「目的」は一つの項目に統合)
・必須記載項目:臨床的意義、今後の展望
・研究内容:[著者の研究内容を入力]
このように具体的に指示することで、学会規定に適合した初稿を得られます。事務局が学会ごとのプロンプトテンプレートを作成・保管することで、対応効率が大幅に向上します。
Q4. AI生成文に著作権はありますか?
A4. 著作権の帰属は、法的に未確定の領域です。
OpenAIやAnthropicの利用規約では、ユーザーが入力したデータに基づいて生成されたテキストは、ユーザーの所有とされていますが、法的に確立した判例はまだ限定的です。
実務的な推奨:
- 学会投稿の場合、生成AIを使用したことを記載する(学会によって要求される場合があります)
- 生成初稿を著者が実質的に確認・修正し、著者の知的成果として投稿する
- 学術団体や大学の倫理委員会に相談し、ガイドラインを確認する
著作権や倫理的側面については、各学会や所属機関の規定に従うことが重要です。
←PREV 第4回:会議記録の作成支援~文字起こしから要点整理まで~
NEXT→ 第6回:学会参加者対応の24時間体制~AIによる問合せ対応の実践~
学術大会・国際会議開催システム「アワード」のご紹介
学会運営における課題を解決し、効率的かつ効果的な運営を実現するために、学術大会・国際会議開催システム「アワード」は以下のニーズにお応えします。
-
1. 学会の効率化と人手不足の解消
学会運営では、事務局の業務量が膨大で、少人数で対応するのが難しい場合もあります。学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、煩雑な運営業務を自動化・効率化することで、人的リソースの負担を軽減します。たとえば、参加登録、プログラム作成、講演者管理などがワンストップで完結します。
-
2. 学会運営のコスト削減
学会開催には、印刷物や郵送、事務局人件費など多くのコストが発生します。学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、クラウドベースでの運営によりこれらのコストを大幅に削減可能。さらに、事務局代行費用を削減しつつ、高品質なサービスを提供します。
-
3. 決済機能でスムーズな収益管理
学会参加費や年会費のオンライン決済に対応。安全性の高い決済システムを導入しているため、事務局での入金確認の手間が省け、効率的な資金管理が可能です。これにより、参加者にも事務局にもストレスフリーな学会運営を実現します。
-
4. 学会運営サポートで「大変」を「簡単」に
「学会運営が大変」と感じている学会事務局の方々に向け、運営全般を支援する学会運営サポートをご用意しています。例えば、会場手配、プログラム編成、スポンサー管理など、運営代行サービスもご紹介可能です。
-
5. 柔軟な管理システムで多様なニーズに対応
学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、学会の規模や形式に応じて柔軟にカスタマイズ可能。オンライン学会、ハイブリッド開催にも対応しており、参加者がどこにいても円滑な学会開催をサポートします。
-
6. 費用対効果の高い学会開催を実現
学会開催費用を抑えつつ、質の高い学会運営を目指す方に最適なソリューションです。クラウド型システムの導入で初期費用を抑え、必要に応じて追加オプションを選択することが可能です。
学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、学会の運営をトータルでサポートし、効率化・コスト削減を実現する強力なパートナーです。学会運営の課題を抱える事務局や運営会社の皆さま、ぜひ一度ご相談ください!





