第6回:学会参加者対応の24時間体制~AIによる問合せ対応の実践~【全10回】
2025.11.19
2026.01.16
はじめに 参加者からの多様な問合せへの対応負担
学会が大会や学術会議を開催する際、参加申込期間から開催当日まで、参加者からの多様な問合せが絶え間なく届きます。
「大会への出席申し込み方法は?」「セッション会場の位置は?」「参加費はいくらですか?」といった基本的な質問から、「キャンセルの手続きは?」「領収書は発行してもらえますか?」「オンライン配信のアクセス方法は?」という個別対応を必要とする質問まで、事務局の負担は非常に大きなものです。
これまでに、第4回では会議記録の作成支援を、第5回では抄録作成の効率化を紹介してきました。同様に、24時間体制の参加者問合せ対応においても、AIチャットボットの導入により、事務局スタッフの対応時間を短縮しながら、参加者の満足度を向上させることが実現できます。
本記事では、過去データの学習から複雑案件の振り分けまで、AIチャットボットを活用した包括的な問合せ対応システムの構築方法を見ていきます。
肝心なのは、AIを「完全自動化ツール」ではなく、「事務局スタッフと参加者の架け橋」として位置づけることです。
参加者の視点に立った対応方法の設計と、スタッフの働き方改革を同時に実現する運営モデルを目指します。
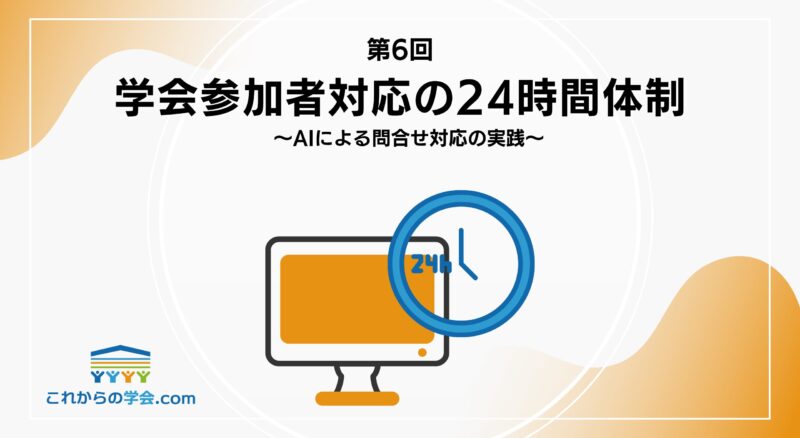
1. AI活用による問合せ対応の実践的方法
1.1. 過去の問合せデータはどのようにAIに学習させ自動返答を実現するのか?
学会が大会を開催する際、毎回同じ質問が参加者から寄せられます。参加費、申込方法、開催地へのアクセス、セッション情報、参加証明書の発行手続きなどは「よくある質問」(FAQ)として体系的に整理することができます。
AIチャットボットに過去のFAQデータを学習させることで、参加者が投げかけた質問に対して、リアルタイムで回答する仕組みが構築できます。
このアプローチにより、基本的な問合せへの対応が効率化され、事務局スタッフはより複雑な業務に注力することが可能になります。
【実践例】User LocalのサポートチャットボットによるFAQ学習
User Localの「サポートチャットボット」は、言語処理に特化したAIを搭載し、言葉のゆらぎ(表記のゆれ)を自動で吸収するため、ユーザーからの曖昧な質問にも適切に対応できるように設計されています。
ステップ1:
過去3年間の参加者問合せメール、問合せフォーム送信内容、電話対応の記録簿などから、頻出する質問とその回答をスプレッドシートやCSV形式で整理します。
参加費や申込方法、アクセス情報など、カテゴリごとにデータを分類することが大切です。
ステップ2:
上記FAQデータを管理画面に登録すれば、「参加費」「参加料」といった表記のゆれを自動で吸収できます。
ステップ3:
試験運用期間を設け、チャットボットの回答精度を検証し、不正確な回答や不自然な表現については、FAQ内容を修正・改善します。
テキストマイニング機能(文章解析)により、チャットボットが対応できなかった質問を可視化でき、継続的な改善に活用することができます。
このプロセスにより、参加者からの基本的な質問の大多数を自動回答で対応でき、事務局スタッフは複雑案件のみに集中できます。
試験運用で得られた改善データは、次年度以降の運用において参考資料となり、組織全体のナレッジとして蓄積されるのがポイントです。
【参考】
・サポートチャットボット|ユーザーローカル
・問い合わせ数を減らすための「FAQサイト」の効果的な作り方|ユーザーローカル
1.2. 申込から当日案内までの包括支援
AIチャットボットの役割は、単なる質問への回答にとどまりません。参加申込から開催当日までの一連のプロセス全体をサポートする設計が重要です。参加者のライフサイクルの各段階で必要とされる情報を、タイムリーに提供することで、参加者体験が飛躍的に向上します。
LINEなどの国内ユーザーの多い身近なツールと連携させて、ユーザーフレンドリーでありながら効率化できる方法もあります。
【実践例】LINE Messaging APIを活用したタイムライン型サポート
LINE Messaging APIにより、双方向コミュニケーションが実現でき、学会の公式LINEアカウントを通じた継続的なサポートが可能になります。
参加者が最初に「友だち追加」すると、段階的なメッセージ配信が実装できます。
申込完了時に、
「申込ありがとうございます。お支払い期限は○月○日です」
「申込から1週間後に「参加準備のご確認。必要な持ち物は…」
「開催3日前に「会場アクセス情報を確認できます」
「Webサイトはこちら」
「開催前日に「明日はいよいよ開催日です。最終確認ガイド」
「開催当日朝に「本日のセッションスケジュール。会場地図はこちら」
というように、参加者が「今知りたい情報」を「必要なときに」受け取ることができます。
また、参加者がLINEチャットで「会場はどこ?」と送信すると、チャットボットが会場地図を返送する仕組みを実装できます。
このアプローチにより、参加者は参加申込から当日まで一貫してサポートを受けられ、従来のメール送信やWebサイト確認による負担が大幅に軽減されます。
さらに、参加者からのフィードバックをリアルタイムで収集でき、次年度以降の改善材料として活用することも可能です。
【FAQ】
Q. 初心者でもLINEのAPIの利用は簡単にできますか?
A. 結論から言うと、プログラミングやWeb開発の基本的な知識があれば可能ですが、全くの初心者(プログラミング未経験者)にとっては「簡単」とは言い難い部分があります。
専門家や信頼のおける開発パートナーに相談することが近道です。
【参考】
・LINE Developers トップページ|LINE
・Messaging APIの概要(日本語)|LINE
・LINE公式アカウントのステップ配信とは?設定方法や配信事例も紹介|LINE
・中小規模学会から利用できる学会開催支援システムを目指して|AWARD
1.3. 多言語対応機能による国際学会への対応
国際学会や海外参加者を受け入れる学会では、英語や中国語など複数言語でのサポートが必須です。
Claude APIやGoogle Geminiなどの多言語対応AIを活用することで、言語の障壁を低減し、参加者の利便性を向上させることができます。
参加者が最初に送信したメッセージの言語をAIが自動判定し、Claude APIに「この言語で回答してください」と指示することで、すべての応答をその言語で行うことができます。
複数言語での応答品質を確認する際は、DeepL Writeなどの翻訳AIツールで検証し、不自然な表現を改善することが重要です。
Google Geminiを活用した場合の多言語対応も同等に可能であり、Google Workspace(Gmail、Googleドキュメント等)との連携が容易であるため、Google環境を既に利用している学会では、追加的なシステム構築を最小化できるという利点があります。
多言語対応により、海外参加者の参加障壁が低減され、学会の国際化が促進されます。参加者が母語でサポートを受けられるという安心感は、学会に対する信頼度向上にもつながります。
【参考】
2. 人間とAIの役割分担と運用上の課題
2.1. AIと人間はどのように問合せを振り分け重要案件への対応を集中させるのか?
AIチャットボットが対応可能な案件(参加費確認、会場アクセス、基本的なセッション情報など)と人間による対応が必要な案件(キャンセル料計算、企業団体割の申請、特別配慮が必要な場合など)を効率的に振り分けることが重要です。
User LocalのサポートチャットボットはWebhookにより、チャットボットが対応できなかった質問を可視化し、自動的に事務局スタッフへの「エスカレーション」(上位者要請)が実行されます。
重要度が高い問合せ(キャンセル申請、クレーム等)には、自動的に優先度タグが付与され、事務局での対応優先度が管理できます。すべての問合せは一つの管理画面に集約され、対応漏れや重複対応が防止されます。このプロセスにより、事務局スタッフは「判断が必要な重要案件」に集中でき、作業効率が向上するだけでなく、スタッフの心理的負担が軽減され、業務満足度の向上につながります。
2.2. 対人コミュニケーションとAIサポートの融合
チャットボットから事務局スタッフへの引継時に、参加者の氏名・参加ID・これまでの会話履歴・チャットボットが理解できなかった点などが自動的に受け渡されます。事務局スタッフは文脈を理解した対応ができるようになり、参加者は「また最初から説明する」という負担を感じることなく、スムーズに問題解決へ進むことができます。
このウォームハンドオフ(温かい引継ぎ)の実装により、参加者の不満が軽減され、サービス品質が向上します。また、AIによる定型業務の自動化により、事務局スタッフは「判断が必要な案件」や「複雑な交渉」に集中できるため、単調な作業による疲労が軽減され、結果としてスタッフの定着率向上やモラルの向上、組織全体の持続可能性の向上につながります。
2.3. AIチャットボットの安全性・正確性を確保するためにはどのような対策が必要か?
回答の正確性、個人情報の保護、システムのセキュリティなど、複数の課題への対策が必要です。FAQ内容の定期更新(月1回以上)、事務局スタッフによる抜き打ちチェック、参加者からのフィードバック収集などが有効です。
個人情報保護については、チャットボットには最小限の個人情報のみを扱わせ、SSLによる通信暗号化、定期的なセキュリティ監査、プライバシーポリシーの明記、管理画面へのアクセス権限制御、データ保持期間の設定などの多層的な対策が重要です。
AIのハルシネーション(hallucination:幻覚)による存在しない情報の生成を防ぐため、FAQデータベースへの依存度を高め生成AIの自由度を制限することが推奨されます。複雑な質問には人間対応へ誘導するプロセスを設定することも有効です。
特に個人情報保護については、学会の倫理委員会やコンプライアンス担当者と事前に相談し、組織全体での統一的な方針を確立することが求められます。
経済産業省の『AI事業者ガイドライン』でも、責任あるAI活用における情報セキュリティの重要性が強調されています。
【参考】
・「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」を取りまとめました|経済産業省
3. 導入方法と運用管理
3.1. チャットボット構築ツールの選定と段階的導入
学会の規模・予算に応じて、最適なツールを選定することがポイントです。導入は一度決定してしまうと、後から別のツールに乗り換えることは技術的・経済的に負担が大きいため、導入前の十分な検討が不可欠です。
小規模学会(年1回、参加者500名以下):
LINE Messaging APIまたはGoogle Gemini + 簡易的なFAQで対応可能であり、初期投資を最小化しながら基本的なサポート機能が実装できます。
中規模学会(年1回、参加者500~2,000名):
User LocalやMicrosoft Power Virtual Agentsが推奨されます。複数の参加者からの質問を効率的に管理し、テキストマイニング機能で継続的改善が可能です。
大規模学会(年複数回、参加者2,000名以上)
User Local + LINE Messaging APIの連携、または多言語対応が必要な場合はDrift(会話型マーケティングプラットフォーム)の導入が推奨されます。複数のプラットフォームを統合することで、包括的で柔軟な対応が実現できます。
3.2. 継続的改善の仕組み
月次で「応答率」「エスカレーション率」「参加者満足度」「システムダウンタイムの有無」をレビューし、データとして記録することが重要です。テキストマイニング機能でチャットボットが対応できなかった質問を抽出し、事務局スタッフが回答を作成してFAQデータベースに追加していくプロセスが、継続的な改善を実現します。
このプロセスを毎月実施することで、チャットボットの対応率が段階的に向上し、年間を通じて継続的に改善されていきます。参加者からの新しい質問パターンに対応することで、システムの機能が組織とともに成長していく実感が得られます。
このような継続的な改善を積み重ねることで、AIチャットボットは学会の運営効率化の中核的なツールへと進化していきます。参加者対応の24時間体制化は、単なる時間短縮ではなく、事務局とAIの協働によって参加支援が充実し、その結果として学会全体の運営水準が向上していくことで、学会と参加者との関係がより良い形で育まれていくと考えられます。
【参考】
・テキストマイニングとは?活用方法やアウトプット例までご紹介!|株式会社プラスアルファ・コンサルティング
・AIテキストマイニング by ユーザーローカル|ユーザーローカル
・Driftとは? | 機能や料金、導入事例をご紹介【キャプテラ】|キャプテラ
まとめ 参加者対応の向上と事務局の持続的発展
学会事務局における参加者問合せ対応のAI活用は、単なる業務効率化ではなく、「24時間体制のサポート提供」と「事務局スタッフの働き方改革」を同時に実現するものです。
User Localなどの特化型チャットボット、LINE Messaging APIなどの汎用プラットフォーム、Claude APIやGoogle Geminiなどの多言語対応AIを組み合わせることで、参加者は24時間体制のサポートと多言語対応を得られ、事務局スタッフは定型業務が効率化され重要案件に集中でき、学会全体では参加者体験の向上と事務局スタッフの離職率低下が実現できます。
重要なのは、AIを「完全自動化ツール」ではなく、「参加者と事務局スタッフの間に立つサポーター」として位置づけることです。最終的な判断や感情的なサポートは人間に委ね、AIは定型業務と基本的な情報提供に専念するという役割分担が、持続可能で参加者満足度の高い学会運営を実現します。
LINE Messaging APIの基本機能から始める、またはUser Localの試用版で試験運用するなど、段階的な導入から始めることが成功の鍵です。小さな成功体験を積み重ねることで、組織全体のAI活用に対する理解と信頼が深まっていきます。
ここまでで紹介した方法は、学会の規模や運営方針に応じてカスタマイズ可能です。参加者対応の質向上と事務局スタッフの働き方改革という二つの目標を同時に達成することで、学会全体の競争力が強化され、将来にわたって持続可能な運営体制が構築されていきます
【参考】
・User Local サポートチャットボット|ユーザーローカル
・Messaging API|LINE Developers
・Messaging API overview | LINE Developers
・Claude 公式サイト|Anthropic
・学会運営の成功事例に学ぶ ~学術イベントを”持続可能”にする運営戦略~|AWRAD
・AI 事業者ガイドライン|経済産業省
←PREV 第5回:論文関連業務の負担軽減~作成支援から査読管理まで、事務局を支えるAI活用~
NEXT→ 第7回:学会ニュースレターの作成支援~AIと協働する魅力的な情報発信~
学術大会・国際会議開催システム「アワード」のご紹介
学会運営における課題を解決し、効率的かつ効果的な運営を実現するために、学術大会・国際会議開催システム「アワード」は以下のニーズにお応えします。
-
1. 学会の効率化と人手不足の解消
学会運営では、事務局の業務量が膨大で、少人数で対応するのが難しい場合もあります。学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、煩雑な運営業務を自動化・効率化することで、人的リソースの負担を軽減します。たとえば、参加登録、プログラム作成、講演者管理などがワンストップで完結します。
-
2. 学会運営のコスト削減
学会開催には、印刷物や郵送、事務局人件費など多くのコストが発生します。学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、クラウドベースでの運営によりこれらのコストを大幅に削減可能。さらに、事務局代行費用を削減しつつ、高品質なサービスを提供します。
-
3. 決済機能でスムーズな収益管理
学会参加費や年会費のオンライン決済に対応。安全性の高い決済システムを導入しているため、事務局での入金確認の手間が省け、効率的な資金管理が可能です。これにより、参加者にも事務局にもストレスフリーな学会運営を実現します。
-
4. 学会運営サポートで「大変」を「簡単」に
「学会運営が大変」と感じている学会事務局の方々に向け、運営全般を支援する学会運営サポートをご用意しています。例えば、会場手配、プログラム編成、スポンサー管理など、運営代行サービスもご紹介可能です。
-
5. 柔軟な管理システムで多様なニーズに対応
学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、学会の規模や形式に応じて柔軟にカスタマイズ可能。オンライン学会、ハイブリッド開催にも対応しており、参加者がどこにいても円滑な学会開催をサポートします。
-
6. 費用対効果の高い学会開催を実現
学会開催費用を抑えつつ、質の高い学会運営を目指す方に最適なソリューションです。クラウド型システムの導入で初期費用を抑え、必要に応じて追加オプションを選択することが可能です。
学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、学会の運営をトータルでサポートし、効率化・コスト削減を実現する強力なパートナーです。学会運営の課題を抱える事務局や運営会社の皆さま、ぜひ一度ご相談ください!





