第8回:業務連携の仕組みづくり【前編】~無料ツールによる統合的な運営~【全10回】
2025.11.21
2026.01.16
業務連携の仕組みづくりは学会の運営では不可欠です。内容も範疇も多岐に渡りますので、ここでは【前編】と【後編】の二部構成でその内容をお届けします。
この前編の要点
✓ 無料ツールによる統合ワークフローの基本設計(6つのツールの役割と連携方法)
✓ 会員情報の一元管理とセグメンテーションの実装手順
✓ イベント企画から運営、事後フォローまでの効率化プロセス
✓ ニュースレターのパーソナライゼーション配信の具体的手法
後編では、部門間情報共有の仕組み、実践的導入方法、運用上の注意点、実際の学会での導入事例を詳しく見ていきます。
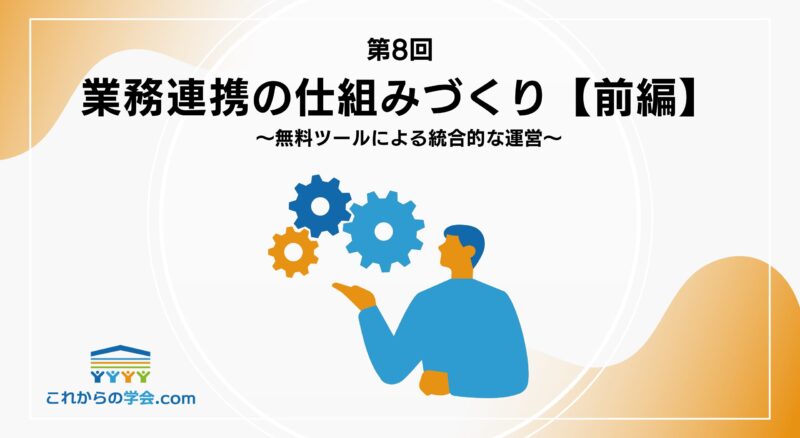
はじめに 中小規模学会における業務統合の課題と可能性
中小規模の学会事務局では、会員管理、イベント企画・運営、ニュースレター配信など、多くの業務が限られたスタッフによって並行して処理されています。これらの業務は相互に関連しながらも、個別のツールやシステムで独立して管理されているため、情報の二重入力や部門間の情報格差といった課題を生じさせています。
こうした運営上の非効率は、スタッフの負担増加だけでなく、会員サービス品質の低下や、学会経営上の意思決定の遅延にも影響します。特に、会員属性情報がチーム間で同期されていなかったり、参加申込データが配信リストに自動反映されなかったりすることは多くの学会で見受けられます。
本記事では、高額な専門ツールに頼らず、無料もしくは無料トライアルで利用できるツールを組み合わせる「無料ツール統合モデル」を検討します。
このモデルは、Google Forms、Google Sheets、Zapier、Notion、Slack、Google Analyticsという6つのツールを戦略的に組み合わせることで、会員管理から効果測定までの一連の業務を、一元的かつ自動化された体系として構築できます。
無料版主要ツール比較表
| ツール名 | 分類 | 無料版の特徴 | 主な制限 | 学会業務への適用例 |
| Slack(無料版) | チャット・コミュニケーション | 基本チャット、ファイル共有 | メッセージ履歴90日、アプリ10個限定、ワークフロー不可 | カスタマイズ性が高い、部門間情報共有に有効だが、長期保存に課題(ファイル共有期間90日) |
| Chatwork(無料版) | チャット・コミュニケーション | 基本チャット、ファイル共有 | 過去40日分まで閲覧、管理者によるユーザー管理は可能(100人まで) | 査読担当者との1対1チャットで進捗確認やリマインド タスク機能で「査読期限」「修正依頼」などを明示 |
| Zapier(無料版) | 自動化・連携ツール | 月100タスク、基本自動化 | 最大5個のZap、実行回数制限 | Google Forms→Sheetsなど基本的な自動化は可能。申込・集計業務の効率化に有効 |
| Notion(無料版) | 情報管理・ナレッジ共有 | 個人は無制限、チーム限定 | 1ファイル5MBまで、Notion AI 20回/月 | 情報管理・ナレッジベース構築に有効。議事録・FAQ・Tips集の整理に活用可能効 |
| Google Workspace 無料版 | オフィス統合ツール | Gmail、Googleドライブ、ドキュメント、スプレッドシート、スライド、Keep、カレンダー、Meetなど | Gmail、Googleドライブ、Googleフォトの容量が共通で15GBまで 法人向けの高度な管理機能やセキュリティ機能(Vault、Cloud Searchなど)は利用できません。 | 会員管理、申込受付、文書作成、スケジュール共有など幅広く活用可能 |
| Google Analytics 4(無料版) | アクセス解析ツール | 完全無料、基本分析機能 | 有料版との設定上限の違いあり | ニュースレターやWeb集客の効果測定に有効。学会サイトのアクセス解析に活用可能 |
| Google Sheets(無料版) | 表計算・データ管理 | 完全無料、容量15GB/Googleアカウント | Google Workspaceの無料版機能に準拠 | 会員名簿、申込一覧、アンケート集計などデータ統合・分析の中心ツールとして活用可能 |
| Google Forms(無料版) | フォーム作成・アンケート | 完全無料、回答数無制限 | テンプレート機能は限定的 | イベント参加申込、アンケート、会員調査に最適。Zapier連携で自動化も可能 |
| Discord(無料版) | チャット・コミュニケーション | 基本チャット機能、ボイス会話 | 高度な権限管理は有料版のみ | Slackの代替・補助として学会内部コミュニケーションに有効。非公式な交流や若手研究者との接点に活用可能 |
| Trello(無料版) | タスク・プロジェクト管理 | 基本タスク管理 | メンバー数やボード数に制限あり | 中小規模学会の初期段階では有効。委員会ごとの進捗管理やイベント準備に活用可能 |
主要ツールの組み合わせ例
| ツール名 | 主な特徴 | 学会業務への適用例 | ||
| Chatwork+Google Forms+Zapier | 申込受付〜進捗共有の自動化 | 参加申込フォーム → Sheets転記 → Chatwork通知。査読依頼の進捗管理とリマインド | ||
| Trello+Google Drive+Chatwork | 委員会業務の進捗管理とファイル共有 | 委員会ごとのタスク管理 → Driveで資料共有 → Chatworkで通知と連携 | ||
| Notion+Google Calendar+Chatwork | ナレッジ管理とスケジュール共有 | FAQや議事録の一元管理 → カレンダーで日程共有 → Chatworkでリマインド | ||
| Google Forms+Google Sheets+Google Drive | 申込・集計・資料管理の一元化 | 参加申込 → 自動集計 → Driveで資料保存・共有 | ||
※2025年10月現在
1. 無料ツールによる統合ワークフローの基本設計【2025年最新版】
1.1 統合ワークフロー全体像と各ツールの役割分担
学会業務を効率的に運営するためには、複数のツールがシームレスに連携する仕組みが欠かせません。以下は、本記事で提案するZapier自動化による統合ワークフローの基本的な流れです。
【統合ワークフローの5つのステップ】
- ステップ1:情報取得(Google Forms):
イベント申込、アンケート、会員情報登録を一元化します。 - ステップ2:自動処理・蓄積(Zapier + Google Sheets):
Formsの回答をSheetsに自動転送し、手作業とヒューマンエラーを防止します。(Zapier無料版は月100タスクまで可能) - ステップ3:統合管理(Notion会員管理データベース):
SheetsのデータをNotionで一元管理し、複雑な条件での情報抽出を可能にします。 - ステップ4:情報共有(Slack):
Notionのデータ更新を自動でSlackに通知し、リアルタイムでの情報共有を促進します。(Slack無料版はメッセージ履歴90日間の制限に注意) - ステップ5:効果測定(Google Analytics + Google Sheets):
ニュースレターのクリック率などをGoogle Analyticsで追跡し、Sheetsで定量的に分析します。
この中で、各ツールは以下の役割を担い、全体として一つの統合システムとして機能します。鍵となるのは、ツール間の連携を自動化し、スタッフの手作業を最小限に抑えることです。
【各ツールの役割と特性の整理】
- Google Forms:入口となるデータ取得ツール。設定が直感的で、会員の利便性が高まります。
- Google Sheets:データの集約と初期処理を担当。リアルタイムでの情報確認が可能になります。
- Zapier:複数のツール間の「橋渡し役」として機能する自動化ツール。プログラミング知識不要で設定できます。
- Notion:情報の長期保存と高度な管理を実現。タグ、フィルター機能により、複雑な情報関係を視覚的に管理できます。
- Slack:リアルタイムコミュニケーションの中核。無料版の履歴制限があるため、Notionと役割分担が効果的です。
- Google Analytics:配信コンテンツや学会ウェブサイトのトラフィック分析に有効です。
【参考】
・Slackのフリープランの機能制限|Slack
・会社全体でひとつのツール チームは無料でトライアル利用ができます。|Notion
1.2 中小規模学会での実装における段階的アプローチ
統合ワークフローを一度にすべて構築しようとすると、導入の複雑さと運用負荷が大きくなります。段階的な導入が、実現可能性を高め、スタッフの学習曲線を緩和する上で効果的です。
【フェーズ1:基礎構築(初月~2ヶ月目)】
会員情報とイベント参加申込の一元化に注力します。Formsでテンプレート化し、Zapierで回答がSheetsに自動入力される仕組みを確立します。導入時は、複数スタッフで運用し問題点をリストアップすることが重要です。
【フェーズ2:統合深化(3~4ヶ月目)】
SheetsのデータをNotionに取り込み、より高度な情報管理を開始します。会員属性とイベント履歴を関連付け、「化学系の大学院生」などセグメント別の情報抽出を可能にします。この段階でSlackとNotionの連携を設定し、Notionの更新を自動通知します。
【フェーズ3:効果測定の組み込み(5ヶ月目以降)】
Google Analyticsでニュースレター内のリンククリックを追跡し、その結果をSheetsに定期的にエクスポートします。これにより、「施策の実施→効果測定→改善提案」という継続的改良サイクルが完成します。
2. 会員管理・イベント運営・ニュースレター配信の統合フロー
2.1 会員情報の一元管理と業務の自動化
学会の会員情報は、施策を支える貴重な資産です。Notionの「データベース」機能を活用すれば、会員情報を中心とした統合管理体系を構築できます。基本情報に加えて、イベント参加履歴、購読状況などを「リレーション」で関連付けます。このアプローチにより、複合的な条件(例:「過去3回連続でイベント参加していない会員」)での抽出が可能になります。
Formsで新規会員登録フォームを作成し、回答がSheets経由でNotionに自動転送される設定にすれば、手作業をほぼゼロにできます。
【実践例:会員セグメンテーションの実装】 Notionのフィルター機能を用いて、以下のようなセグメンテーションが可能です。
- 職位別:大学院生、研究員、大学教職員、企業研究者
- 専門分野別:化学、物理、生物、工学など
- 関与度別:過去1年のイベント参加回数で分類
これらのセグメントは、イベント企画やニュースレター配信の際に、ターゲットとなる会員グループを自動抽出する際に活用されます。
2.2 イベント企画・運営フローの効率化
Google Forms、Google Sheets、Notionを組み合わせることで、イベントの企画から事後フォローアップまでのプロセス全体を可視化し、自動化できます。
- 企画段階:
Notionで「イベント企画テンプレート」を作成し、開催日時、対象者、予算などを一覧化します。タイムラインビューにより、視覚的な進捗管理が可能です。 - 参加申込:
Google Formsで申込フォームを作成し、回答をSheets経由でNotionに自動転送します。参加者の属性情報も記録されるため、傾向分析に活用できます。 - 運営・実施:
SlackのイベントチャネルでZapierを通じた自動リマインダーを配信し、事前通知を効率化します。イベント記録はNotionに集約することが必須です。 - 事後フォローアップ:
Formsで「参加者アンケート」を配信し、結果をSheets→Notionを通じて自動的に記録します。過去のイベントデータを蓄積することで、次回の企画立案に役立つ傾向分析が可能になります。
このフローで大切なのは、すべての情報が一つの情報体系(Notion)に集約されることです。
2.3 ニュースレター配信とセグメント別パーソナライゼーション
従来のニュースレターは、全会員へ一律の内容を配信することが一般的でしたが、これは読者の関心度に合致しないため、開封率やエンゲージメントの低下を招きます。本ワークフローでは、Notionで一元管理された会員の属性情報(専門分野、職種、所属など)に基づき、配信内容を最適化する「パーソナライゼーション配信」を実現します。
この仕組みは、会員に「自分事」として情報を受け取ってもらうための重要なステップであり、以下の手順で実装されます。
【実装手順】
- セグメントのフィルタリング:Notionのデータベースから、特定の条件に該当する会員グループをフィルタリングします。
- データエクスポート:抽出した会員リストをCSVファイルとしてエクスポートします。
- 配信ツールへのインポート:CSVファイルを、メール配信ツール(例:Mailchimp)にインポートします。
- 自動配信の設定:配信ツール上で、セグメント別のメールテンプレートを設定し、自動配信します。
このプロセスはZapierを活用することで、さらに自動化できます。
【AIを活用したコンテンツ生成の具体的な応用】
第7回で紹介したAIによるコンテンツ生成の技術は、このニュースレター配信において極めて有効です。
- 件名のA/Bテスト最適化セグメント:別に配信する際、それぞれの読者層の関心度に合わせた複数の件名案をAI(例:Notion AIやChatGPT)に生成させ、配信ツールのA/Bテスト機能を利用して最適化を図ります。
- パーソナライズされた導入文:会員の専門分野に基づき、「〇〇研究に携わる皆様へ」といった導入文や、最新の研究動向に関する要約文をAIで自動生成することで、より一層の開封率とエンゲージメントの向上が期待できます。
これらの手法により、開封率やクリック率の大幅な向上が期待できます。
【参考】
・Turn Emails into Revenue|Mailchimp
・A/Bテストとは?初心者にもわかる基本と実践ガイド|Kajabi Japan
・ABテストとは?王道4つの分析パターンとおすすめツールまとめ|LISKUL
前編のまとめと後編のポイント
本記事の前編では、無料ツールによる統合ワークフローの基本設計と、会員管理・イベント運営・ニュースレター配信の統合フローについて解説しました。Google Forms、Google Sheets、Zapier、Notionを中心とした自動化により、学会事務局の業務効率を大幅に向上させることが可能です。
前編のポイント
- 6つのツールの役割分担と連携方法
- 会員セグメンテーションの実装手順
- イベント運営の効率化プロセス
- パーソナライゼーション配信の具体的手法
【導入前チェックリスト】
統合ワークフローの導入を開始する前に、以下の項目を確認してください。
□ 組織体制の確認
- システム管理者候補(1名)が決定している
- データ入力・管理者候補(1~2名)が決定している
- 配信・企画担当者候補(1~2名)が決定している
- 理事会・事務局の承認を得ている
□ 現状業務の把握
- 現在の業務にかかる時間を計測している(会員管理、イベント運営、配信など)
- 現在使用しているツール・システムをリストアップしている
- 業務上の課題と改善希望をスタッフから収集している
□ ツール環境の準備
- Googleアカウント(学会用)を取得している
- 各スタッフのGoogleアカウントでのアクセス権限を検討している
- 無料版の制限内容を理解している(Slack 90日、Zapier 月100タスクなど)
□ データの整理
- 現在の会員リストがデジタル形式(ExcelまたはCSV)で存在する
- 過去のイベント参加記録が整理されている
- 個人情報保護の方針が確認されている
□ 学習リソースの確保
- YouTube等の無料チュートリアルをリストアップしている
- 各ツールの公式ヘルプページをブックマークしている
- 週2回、30分の学習時間を確保できる
□ 試行期間の設定
- 最初の3ヶ月を試行期間として設定している
- 小規模なイベント(内部勉強会など)から試行することを計画している
- 月1回の振り返りミーティングの日程を決めている
このチェックリストを満たすことで、スムーズな導入が可能になります。すべての項目を完璧に満たす必要はありませんが、組織体制の確認と現状業務の把握は必須です。
後編のポイント
✓ 複数部門(理事会、事務局、委員会)間での効果的な情報共有の仕組み
✓ 意思決定プロセスの可視化と記録管理の手法
✓ 実践的な導入方法(人員配置、学習支援、運用マニュアル)
✓ データセキュリティとリスク管理の具体的対策
✓ 実際の学会(物質科学学会、歴史学研究会、都市社会学会)での導入事例と効果測定
✓導入時のよくある失敗例
第7回のニュースレター制作支援と組み合わせることで、学会運営全体の効率化と質的向上が達成できます。
→ 後編はこちら
後編では、部門間情報共有の仕組みと実践的導入方法、複数の学会事例を詳しく解説します
←PREV 第7回:学会ニュースレターの作成支援~AIと協働する魅力的な情報発信~
NEXT→ 第8回:業務連携の仕組みづくり~無料ツールによる統合的な運営~【後編】
学術大会・国際会議開催システム「アワード」のご紹介
学会運営における課題を解決し、効率的かつ効果的な運営を実現するために、学術大会・国際会議開催システム「アワード」は以下のニーズにお応えします。
-
1. 学会の効率化と人手不足の解消
学会運営では、事務局の業務量が膨大で、少人数で対応するのが難しい場合もあります。学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、煩雑な運営業務を自動化・効率化することで、人的リソースの負担を軽減します。たとえば、参加登録、プログラム作成、講演者管理などがワンストップで完結します。
-
2. 学会運営のコスト削減
学会開催には、印刷物や郵送、事務局人件費など多くのコストが発生します。学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、クラウドベースでの運営によりこれらのコストを大幅に削減可能。さらに、事務局代行費用を削減しつつ、高品質なサービスを提供します。
-
3. 決済機能でスムーズな収益管理
学会参加費や年会費のオンライン決済に対応。安全性の高い決済システムを導入しているため、事務局での入金確認の手間が省け、効率的な資金管理が可能です。これにより、参加者にも事務局にもストレスフリーな学会運営を実現します。
-
4. 学会運営サポートで「大変」を「簡単」に
「学会運営が大変」と感じている学会事務局の方々に向け、運営全般を支援する学会運営サポートをご用意しています。例えば、会場手配、プログラム編成、スポンサー管理など、運営代行サービスもご紹介可能です。
-
5. 柔軟な管理システムで多様なニーズに対応
学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、学会の規模や形式に応じて柔軟にカスタマイズ可能。オンライン学会、ハイブリッド開催にも対応しており、参加者がどこにいても円滑な学会開催をサポートします。
-
6. 費用対効果の高い学会開催を実現
学会開催費用を抑えつつ、質の高い学会運営を目指す方に最適なソリューションです。クラウド型システムの導入で初期費用を抑え、必要に応じて追加オプションを選択することが可能です。
学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、学会の運営をトータルでサポートし、効率化・コスト削減を実現する強力なパートナーです。学会運営の課題を抱える事務局や運営会社の皆さま、ぜひ一度ご相談ください!





