学会における抄録の書き方とは
2022.12.16
2025.01.10
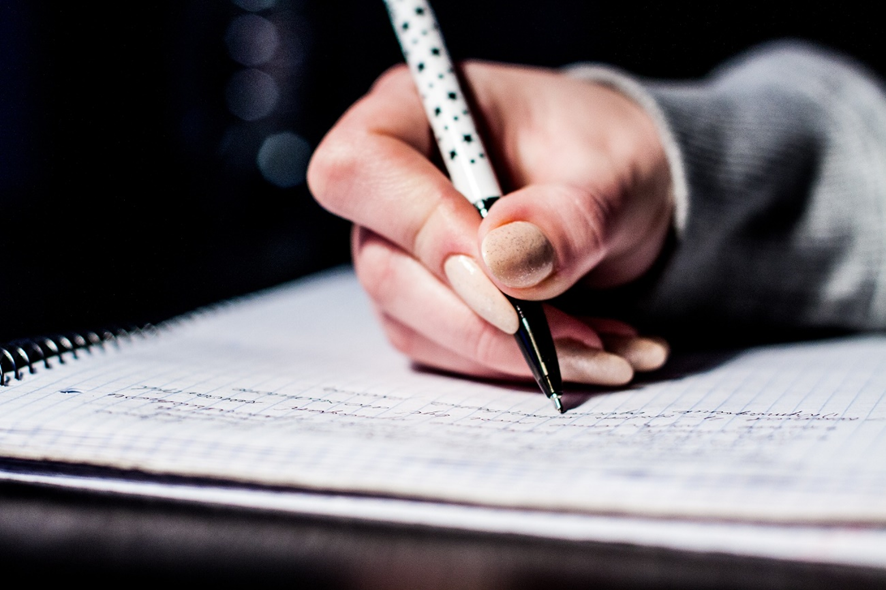
研究を続け、ある程度の成果が出たら世界に向けて発信しなくてはなりません。どれだけ人の役に立つような研究結果が出ても公表していなければ勿体ないです。そんな研究結果を発表する場の1つが学会です。
そして学会発表をするには、抄録というものを作成し学会に登録をしなければなりません。とはいっても、抄録はどのように書くのが正解なのかと悩んでいる人も少なくないでしょう。そこでこの記事では、抄録の書き方や注意点まで紹介していきたいと思います。是非参考にしてみてください。
そもそも抄録とは

抄録は研究した成果をまとめた研究論文を分かりやすく要約したものです。一般的には、400から1500文字程度の文字数でまとめられています。複数人の抄録をまとめた抄録集への印刷の都合もあるので、かなり端的に研究結果をまとめる必要があります。
この抄録集を読むことで学会参加者は、研究内容や研究結果を短い時間で把握することができます。読者側にいかに分かりやすく、伝えたいことを伝えられるまとめ方ができているかが抄録を書く上では重要になってくるでしょう。
学会発表をするためには、抄録の提出を求められます。論文の査読ほどではありませんが学会運営者側のチェックが入ります。文字数や抄録の体裁、倫理事項などのチェックが入るため学会規定など確認事項をしっかりと読み込んで提出するようにしましょう。
抄録の構成は?

抄録は通常「背景・目的・方法・結果・考察・結語」という6項目で構成されています。文字制限などの理由からやむを得ない場合は、考察と結語は省略しても問題ないとされていることもあります。※学会規定をご確認ください。
ここでは、6項目それぞれの書き方やどんな内容を記載していくのかをご紹介していきます。
背景
背景は、あなたが行った研究を行うに至った経緯を書くブロックになります。背景では、研究の問題を解くことについての意義を説明することがコツです。研究によりどんな問題を解決しようとしているのか、どのようなことが前提条件として解明されているのか、未解明な部分はどこなのかを分かりやすく記載してください。
目的
目的は、背景を踏まえたうえで学会発表や論文にてその研究で明らかにしたいことを記載します。
具体的にどんな問題を解決し、解明することが研究のゴールなのか、そのゴールに向かうために研究自体のどこに新規性があるのかを記載するようにしましょう。
方法
方法は、対象者や研究手順、解析の方法を書きます。簡潔に書かなければいけない抄録において一番ボリュームのある部分です。
ボリュームがあるがゆえに、書かなくてもいいことまで書きがちになってしまいますので注意しましょう。例えば、対象者は除外基準や条件などは書かずに対象とした人の情報のみを記載するようにします。解析方法は、具体的な方法名などはいらずAとBを
ただし、研究手順はどのような手順で何のデータを取ったのかが分かるようにしっかりと書き込むようにしましょう。
結果
1つの研究からは求めていた結果と共に副次的な結果が出る場合もあります。しかし、抄録には副次的な結果は記入せず、主要な研究結果だけを記入するようにしましょう。
結果は、数値や客観的指標で記載します。統計学的な解析結果を抄録に書き込む場合は、国際的に推奨されている形式を使用してください。
研究全体の結果といった大きな研究結果を先に書き、各実験の詳細な結果を書くと見やすい抄録になるでしょう。
考察
考察では、研究結果から見えてくることを簡潔に記していきます。研究結果1つ1つに考察を加えていくと文字数が足りなくなるので、研究結果のみか今回の研究を総括した考察だけを書くようにしましょう。
結語
結語はいわゆるまとめみたいなものです。背景、目的、方法、結果、考察を上手くまとめて抄録に書かれていることの流れが分かるようにできるとよいでしょう。
例えば、「背景は○○で○○を解き明かすことを目的に、○○という方法で実験を行ったところ○○という結果が得られた。この結果から見えてくることは○○です。今後は○○といった視点から詳細な研究を行おうと考えている。」といった具合です。
抄録を書く場合の注意点

ここまでで抄録に書く内容は分かったと思います。ここからは、抄録を作る際に注意しなければならない点を解説していきます。
引用の使い方
他の参考文献から引用をする場合には、どの文章が引用箇所なのかを明確に表示する必要があります。引用した文献は、最後に参考文献として明示しておきましょう。
文字数の制約
抄録には文字制限が設定されている場合があります。文字の大きさやページ制限がある学会もあり、学会の規約をしっかりと把握しておかなければ内容以前に弾かれてしまうことがあるため注意が必要です。
語尾は「である」調で
語尾は「ですます調」ではなく、「である調」を使用するようにしましょう。論文では理論的で客観的な事実を記載しなければなりません。「ですます調」は丁寧な印象を与えることができますが、断定的で信頼性のある印象はあたえられません。しっかりと「である調」になっているかを確認しましょう。
また、体言止めなども使う事はしない方がよいでしょう。
著者・共同著者の掲載順は研究への貢献度を考慮する
著者が何人かいる場合には貢献度順で名前を記載していくことになります。研究主導者は筆頭著者と呼ばれており、1番最初に記載するべき人です。
読者は抄録を読んだだけでは誰がどのくらいの貢献をしているのかが分からないため、しっかりと貢献度順に名前を記載するようにしましょう。
執筆後のチェック依頼
抄録の作成後は、共同著者など自分以外の人にチェックしてもらうことを心がけましょう。要約して書いていくなかで、研究の内容が分かりにくいものになっている可能性があるため確認してもらう事は重要です。
また抄録の最後には指導や支援を受けた相手に対して感謝の意を示すため、謝辞の欄を作りましょう。研究データを提供した個人や組織、研究設備を提供した個人や組織、研究資金提供者などが主な対象となります。
学術大会・国際会議開催システム「アワード」のご紹介
学会運営における課題を解決し、効率的かつ効果的な運営を実現するために、学術大会・国際会議開催システム「アワード」は以下のニーズにお応えします。
-
1. 学会の効率化と人手不足の解消
学会運営では、事務局の業務量が膨大で、少人数で対応するのが難しい場合もあります。学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、煩雑な運営業務を自動化・効率化することで、人的リソースの負担を軽減します。たとえば、参加登録、プログラム作成、講演者管理などがワンストップで完結します。
-
2. 学会運営のコスト削減
学会開催には、印刷物や郵送、事務局人件費など多くのコストが発生します。学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、クラウドベースでの運営によりこれらのコストを大幅に削減可能。さらに、事務局代行費用を削減しつつ、高品質なサービスを提供します。
-
3. 決済機能でスムーズな収益管理
学会参加費や年会費のオンライン決済に対応。安全性の高い決済システムを導入しているため、事務局での入金確認の手間が省け、効率的な資金管理が可能です。これにより、参加者にも事務局にもストレスフリーな学会運営を実現します。
-
4. 学会運営サポートで「大変」を「簡単」に
「学会運営が大変」と感じている学会事務局の方々に向け、運営全般を支援する学会運営サポートをご用意しています。例えば、会場手配、プログラム編成、スポンサー管理など、運営代行サービスもご紹介可能です。
-
5. 柔軟な管理システムで多様なニーズに対応
学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、学会の規模や形式に応じて柔軟にカスタマイズ可能。オンライン学会、ハイブリッド開催にも対応しており、参加者がどこにいても円滑な学会開催をサポートします。
-
6. 費用対効果の高い学会開催を実現
学会開催費用を抑えつつ、質の高い学会運営を目指す方に最適なソリューションです。クラウド型システムの導入で初期費用を抑え、必要に応じて追加オプションを選択することが可能です。
学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、学会の運営をトータルでサポートし、効率化・コスト削減を実現する強力なパートナーです。学会運営の課題を抱える事務局や運営会社の皆さま、ぜひ一度ご相談ください!





