【解説】 AIツールと個人情報保護:学会事務局のための実践ガイド
2025.11.17
2025.11.20
はじめに AIツールと個人情報保護の交差点
生成AIの導入が不可避となった今、学会事務局が直面する最大のリスクは、『知らないうちに』個人情報を流出させることです。
学会事務局では、会員の氏名・所属・メールアドレスに加え、研究テーマ、未発表の研究計画、査読過程での評価コメント、国際共同研究に関わる海外研究者情報など、高度な機密性を持つデータを日常的に扱っています。
ChatGPTをはじめとする生成AIツールは業務効率化の可能性をもたらす一方で、個人情報保護の観点から新たなリスクも生んでいます。議事録作成の時間短縮、会員対応の迅速化、英語での国際会議運営の容易化など恩恵は多岐にわたりますが、この利便性の背後には重大なリスクが潜んでいます。
実際、企業で社員情報をAIツールに入力した結果、それが学習データとして利用され、他ユーザーの回答に断片的に表示される事例が報告されています。同様の事態は学会でも起こり得ます。利用料が無料という理由でAIツールを選択し、後になって個人情報保護上の重大な問題に気づく事例も少なくありません。
本記事では、AIツール利用において学会事務局が検討すべき三つの重要領域を解説します。第一に法的義務の理解、第二に実践的な安全対策、第三に危機管理です。これら三つを理解することで、AIの恩恵を最大限に享受しつつ、法的安全性を担保することを目指します。
【参考】
・生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について|個人情報保護委員会
・ChatGPTで情報漏洩は起こる?対策や履歴オフの設定方法を解説|株式会社インターコム
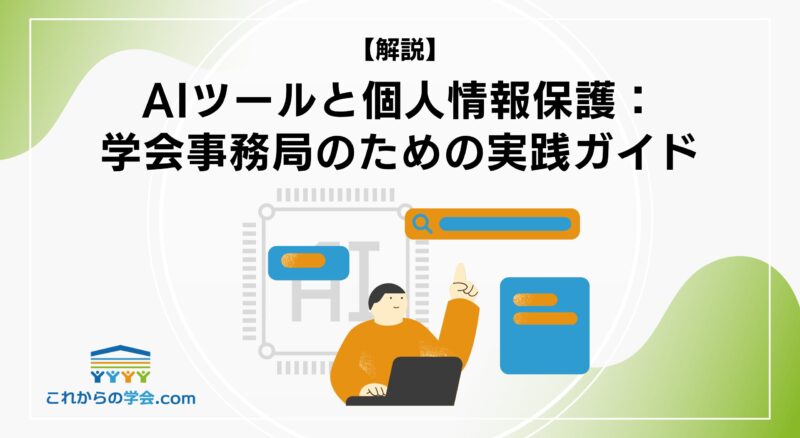
1. 法的義務の理解:個人情報保護法、GDPR、著作権法
AIツール利用が法的に問題ないかを判断するには、まずAIを「開発・学習するフェーズ」と「利用・運用するフェーズ」に区別し、適用法令を確認しましょう。
1.1 日本国内法:個人情報保護法が定める「3つの壁」
日本の個人情報保護法(2022年改正施行)は、AI利用における最も基本的な「壁」を定めています。
目的の壁:
- 取得時の利用目的を本人に通知・公表し、その範囲内でのみ利用します。
- 会員管理のために取得したメールアドレスを、本人の同意なくAI論文推薦サービスに流用することは目的外利用となり、原則禁止されます。
取得の壁:
- 原則として本人の同意を得て個人情報を取得する必要があり、第三者提供にも同意が必要です。
- 学会入会時の同意書に「AIツールを用いた業務効率化のためのデータ利用」を明記するなど、具体的な同意取得プロセスの整備が要求されます。
提供の壁:
- 原則として本人の同意なく第三者へ個人情報を提供できません。
- 提供記録の作成や開示請求への対応も義務化されています。
AIツールへのデータ入力における注意点
AIツールへのデータ入力は、「個人情報の第三者提供」または「委託」のいずれかに該当する可能性があります。いずれの場合も、個人情報取扱事業者は利用目的を特定し、その範囲内でデータを取り扱わなければなりません。
特に、AIツールにプロンプトとして個人情報を入力する行為は、本人が予期しない形で情報が流出し、目的外利用となる深刻なリスクを内包しています。
利用規約を確認し、入力データがAIの学習に利用されないことを事業者との間で明確に担保する必要があります。
安全管理措置の徹底と委託先の監督
個人情報取扱事業者は、個人データに対する不正アクセス、紛失、漏洩を防ぐため、組織的・人的・物理的・技術的な安全管理措置を講じなければなりません。
AIツール提供事業者を「委託先」と位置づける場合、委託先が講じる安全管理措置が適切であるかを選定時に確認し、必要かつ適切な監督を行う義務が課せられます。
【参考】
・AI事業者ガイドライン|経済産業省
・個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)|個人情報保護委員会
1.2 国際法:GDPR準拠のためのDPIA(データ保護影響評価)
国際的な個人情報保護規則では、GDPR(EU一般データ保護規則)がAI利用に対して特に厳格な基準を要求しています。EU域内(EEA)の個人データを扱う日本の学会も適用対象です。日EU間の相互認証(2019年1月23日)により、日本は「十分性認定」を受けていますが、GDPR基準の遵守は必須です。
AIが大規模なプロファイリングや、センシティブな個人データの処理を行う場合、GDPR第35条に基づき、DPIA(Data Protection Impact Assessment:データ保護影響評価)という事前に問題点をチェックする仕組みの実施が義務付けられます。これは、処理開始前に潜在的リスクを評価し、軽減策を講じるプロセスです。国際会員のデータを扱う学会にとって、DPIAは必須の手続きです。GDPR違反があった場合、全世界売上高の最大4%または2,000万ユーロのいずれか高い方という巨額の制裁金が課される可能性があるため、国際学会では最優先で着手すべき課題です。
【参考】
・日EU間・日英間のデータ越境移転について|個人情報保護委員会
・EU一般データ保護規則(GDPR)に関わる実務ハンドブック(入門編)|JETRO
1.3 著作権法:AI学習データと利用の境界線
AIツールでコンテンツを生成する際、著作権侵害のリスクも考慮しなければなりません。
日本著作権法第30条の4(平成30年改正、2019年1月施行)は、「情報解析を目的とする場合」(AI学習)の著作物利用を原則として許容しており、日本のAI開発を後押ししています。
文化庁が2024年3月に公表した「AIと著作権に関する考え方について」では、AI開発・学習段階と生成・利用段階を明確に区別し、それぞれの著作権法上の取扱いを整理しています。
特に注意すべきは、AIの学習に利用されるデータが適法に収集されたものか、またその利用が将来的な著作権者の利益を不当に害さないかという点です。
AI技術の進化に伴い解釈は変化する可能性があるため、最新の判例や政府見解を定期的に確認することが期待されています。
AIツールの出力結果が既存著作物と酷似し、「表現が同一または類似」と判断される場合は著作権侵害となる可能性があります。AIツールで記事や要旨の作成、翻訳を行う場合は、その出力結果に「人間による創作的な関与」を加え、オリジナリティを確保するプロセスが肝要です。
文化庁は2024年7月に「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」を公表しており、AI利用者が確認すべき事項を具体的に示しています。
【参考】
・AIと著作権について|文化庁
・AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス(令和6年7月31日)|文化庁著作権課
2. 実践的な安全対策
2.1 データ入力制限と匿名化の徹底
学会内ガイドラインを策定する際には、重要な個人情報や機密性の高い情報を「うっかり」入力してしまわないよう、まずは全面的に入力を禁止するルールを設けることです。
特に秘匿性の高い研究データや未発表の評価コメントは、外部流出時の影響が甚大です。
ガイドラインは、具体的な事例に基づき「何が禁止されているか」を明確に示し、関係者全員に周知徹底させる義務があります。
禁止対象の例として、氏名・メールアドレス・所属機関名などの識別情報、査読コメントや研究計画書などの機密情報、未成年会員の情報、国際共同研究に関わる海外研究者の個人情報などが挙げられます。
また、データをAIに入力する前に、「匿名加工情報」または「仮名加工情報」としての処理を徹底します。具体的には、ハッシュ化、マスキング、一般化といった手法を用いて、個人特定性を確実に排除する作業が要ります。
2.2 サービス選定における重要視点
AIツールを選定する際は、価格や機能だけでなく、次の項目を厳しく審査する必要があります。
非学習利用の保証(オプトアウト):
- 入力データがAIモデルの学習に利用されないことを利用規約またはSLA(Service Level Agreement:サービス品質保証契約)で明確に保証しているか
- OpenAI社のChatGPT Enterprise、Anthropic社のClaude for Work、Google社のGemini for Workspaceなど、ビジネス向けプランでは入力データの学習利用をオプトアウトできる仕組みが提供されています。
この保証がない場合は、そのツールの利用を直ちに中止するか、機密情報を含まないデータのみに利用を限定することが推奨されます
ログと監査の機能:
- 「誰が」「いつ」「どのような」データを入力し、どのような出力を得たかのログが取得・監査できる仕組みがあり、トレーサビリティを確保できるか
- インシデント発生時の原因究明を可能にするため、ログの保持期間やアクセス権限の確認が必要
【参考】
・AIセキュリティに関する検討について|総務省
・情報セキュリティ|情報処理推進機構(IPA)
3. 危機管理:情報漏洩時の対応
3.1 漏洩発生時の法的義務
万が一、AIツール利用を通じて個人情報が漏洩した場合、個人情報保護法は事業者に対して個人情報保護委員会への報告義務と本人への通知義務を課しています。
特に以下の重大事態に該当する場合、速報(事態を知ってから概ね3〜5日以内)と確報(30日以内、不正目的の場合は60日以内)が必要です。
- 要配慮個人情報が含まれる場合
- 財産的被害が生じるおそれがある情報が含まれる場合
- 不正な目的をもって行われたおそれがある場
- 1,000人を超える個人の情報が含まれる場合
漏洩時の対応は、初動の遅れが信用失墜に直結します。「誰が」「いつ」「どこへ」「何を」報告するかという組織的な対応フローを事前に明文化し、担当者の教育・研修を徹底することも求められています。
【参考】
・漏えい等の対応とお役立ち資料|個人情報保護委員会
・「要配慮個人情報」とはどのようなものを指しますか。また「要配慮個人情報」にかかる留意点は何でしょうか。|個人情報保護委員会
3.2 再発防止とサイバー保険
再発防止には、技術的対策と組織的対策の両面からのアプローチが必要です。
技術的対策としては、多要素認証(MFA :Multi-Factor Authentication)の導入、データ損失防止(DLP:Data Loss Prevention)ツールの活用、暗号化の徹底、アクセスログの監視強化などが挙げられます。
組織的対策としては、個人情報取扱規程の改訂、研修の充実、内部監査の実施、インシデント対応マニュアルの整備が重要です。
万が一に備えてサイバー保険の活用も検討に値します。調査費用、法律費用、通知費用、損害賠償金、見舞金、信用回復費用などがカバーされます。会員数1,000名規模の学会において、年間保険料は10万円から30万円程度が一般的です。保険加入自体が組織のセキュリティレベル向上にも寄与します。
【参考】
・中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン|IPA
・サイバーリスク保険|東京海上日動火災保険株式会社
・サイバープロテクター|三井住友海上火災保険株式会社
・サイバー保険|損害保険ジャパン株式会社
3.3 継続的なリスク管理のPDCAサイクル
情報セキュリティは一度対策を講じれば完了するものではありません。
年度初めにリスクアセスメントを実施し(Plan)、ガイドラインの運用を継続します(Do)。定期的に内部監査を実施し(Check)、インシデント発生時はその原因を分析します。評価段階で明らかになった課題を洗い出し、ガイドラインの見直しを行います(Act)。
AI技術の進化に伴い、規制環境も急速に変化しているため、少なくとも四半期ごとの情報収集と年次での全体見直しが勧奨されます。
【参考】
・PDCAサイクルによるサイバーセキュリティ対策の継続的改善|IPA
まとめ AIとの賢明な共存に向けて
AIツールは学会事務局の業務を劇的に効率化します。議事録作成の時間短縮、会員対応の迅速化、多言語対応の容易化など、その恩恵は計り知れません。
しかし、その利便性と引き換えに、会員の個人情報保護や学術的独立性を犠牲にすることは許されません。
本記事で解説した3つの柱、①法的義務の理解 ②実践的な安全対策 ③危機管理は、相互に関連し合いながら学会の情報セキュリティ体制を支える基盤となります。
特に重要なのは、予防原則に基づく姿勢です。
「転ばぬ先の杖」
漏洩が発生してから対応するのではなく、漏洩を防止する仕組みを事前に構築することが最も費用対効果の高い対策となります。
学会の質の向上と社会的責任を果たすために
学会の質の向上と社会的責任を果たすために、まず今日から次の3点を確認してみましょう。
第一に、現在使用中のAIツールの利用規約を精査し、個人情報保護の観点から適切なサービスであるかを検証することです。特に無料プランを使用している場合は、入力データの学習利用の有無を確認し、必要に応じて有料のビジネスプランへの移行を検討してください。
第二に、個人情報を含むデータのAIツールへの入力に関する明文化されたガイドラインを策定し、組織全体で共有することです。どのツールを使用可能とするか、どのような情報の入力を禁止するか、匿名化処理の手順をどのように定めるかを具体的に規定し、関係者に周知することが大切です。
第三に、情報漏洩時の組織的対応体制を整備し、個人情報保護委員会への報告フローや本人通知の方法について、担当者と手順を明確に定めることです。この体制は一度作って終わりではなく、最新の技術動向と法改正に合わせて継続的に見直し、改善していく必要があります。
AIツールは、正確に理解し、適切に管理することで、学会活動を大きく前進させる有用なツールとなります。技術の進歩を恐れるのではなく、賢明に活用する姿勢がこれからの学会運営において重要です。
会員の信頼は長い年月をかけて築き上げられますが、短期間で失われる可能性も存在します。日本の諺に「築城三年落城一日」という教えがあるように、小さな不信が一瞬にして全てを覆します。
完璧である必要はありません。できることから一つずつ始め、小さな改善を積み重ねることで、会員の信頼を守る強固な基盤を築くことができます。適切な対策を着実に実行することで、社会と会員の信頼を守る基盤となります。
【参考】
学術大会・国際会議開催システム「アワード」のご紹介
学会運営における課題を解決し、効率的かつ効果的な運営を実現するために、学術大会・国際会議開催システム「アワード」は以下のニーズにお応えします。
-
1. 学会の効率化と人手不足の解消
学会運営では、事務局の業務量が膨大で、少人数で対応するのが難しい場合もあります。学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、煩雑な運営業務を自動化・効率化することで、人的リソースの負担を軽減します。たとえば、参加登録、プログラム作成、講演者管理などがワンストップで完結します。
-
2. 学会運営のコスト削減
学会開催には、印刷物や郵送、事務局人件費など多くのコストが発生します。学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、クラウドベースでの運営によりこれらのコストを大幅に削減可能。さらに、事務局代行費用を削減しつつ、高品質なサービスを提供します。
-
3. 決済機能でスムーズな収益管理
学会参加費や年会費のオンライン決済に対応。安全性の高い決済システムを導入しているため、事務局での入金確認の手間が省け、効率的な資金管理が可能です。これにより、参加者にも事務局にもストレスフリーな学会運営を実現します。
-
4. 学会運営サポートで「大変」を「簡単」に
「学会運営が大変」と感じている学会事務局の方々に向け、運営全般を支援する学会運営サポートをご用意しています。例えば、会場手配、プログラム編成、スポンサー管理など、運営代行サービスもご紹介可能です。
-
5. 柔軟な管理システムで多様なニーズに対応
学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、学会の規模や形式に応じて柔軟にカスタマイズ可能。オンライン学会、ハイブリッド開催にも対応しており、参加者がどこにいても円滑な学会開催をサポートします。
-
6. 費用対効果の高い学会開催を実現
学会開催費用を抑えつつ、質の高い学会運営を目指す方に最適なソリューションです。クラウド型システムの導入で初期費用を抑え、必要に応じて追加オプションを選択することが可能です。
学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、学会の運営をトータルでサポートし、効率化・コスト削減を実現する強力なパートナーです。学会運営の課題を抱える事務局や運営会社の皆さま、ぜひ一度ご相談ください!





