【Tips】統合的なAI活用環境の必要性への気づき
2025.11.28
2025.11.28
はじめに
これまでの連載を通じて、学会事務局の個別業務(会員管理、広報、問合せ対応、議事録作成など)にAIツール(ChatGPT、Claude、Otter.aiなど)を導入し、一定の効率化を実現する方法を検討してきました。この「タスク単位の効率化」はAI導入の第一段階として極めて重要です。
しかし、多くの事務局が次の段階で直面するのが、情報と機能の「分断」という課題です。会員情報はスプレッドシートに、問合せ履歴はチャットボットシステムに、広報記事のドラフトは汎用AIツール内に、といった具合に、情報がそれぞれのツール内に閉じ込められ、有機的に連携しない状態、すなわち「サイロ化」が生じています。
AI活用の真価は、データと機能が連携する統合環境で発揮されます。本記事では、「個別最適」から「全体最適」への転換がもたらす効果を考察します。
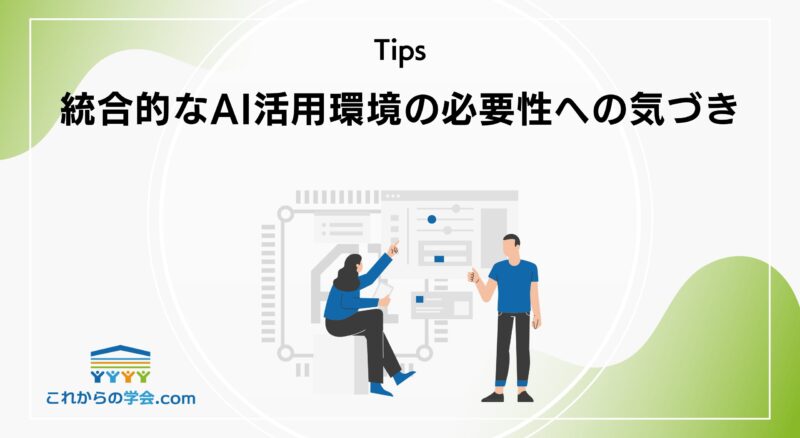
1. 個別AI導入の限界と業務の「サイロ化」
学会事務局の業務は、委員会運営、広報、大会参加者対応、そして財務・経理といった多様なプロセスが、時系列または論理的に連携して成り立っています。この連携の過程で、情報が分断されることは大きな非効率性を生み出します。
1.1. ツール間の情報移動コストの増大
特定の業務に特化したAI(特化型AI)や、文書生成に優れた汎用AI(ChatGPT、Copilotなど)は、そのタスク内では優れた成果を出します。しかし、次の業務フェーズに移る際、スタッフは必ず情報の手動移動を強いられます。
- データ連携の非効率: 委員会メンバーの出欠データ(Google Forms)を、活動報告書の作成(Google ドキュメント/AI生成)に利用する場合、手動でのコピー&ペーストや形式変換が必要です。この手間は、特に頻繁に発生する定型業務において、AIが削減したはずの作業時間を相殺してしまう可能性があります。
- 知識の断片化: 大会参加者からの問合せ対応でチャットボットが回答を生成しても、その履歴が会員情報データベースや過去の大会運営資料と連携していない場合、「なぜその質問が多いのか」「この質問をした会員はどのような属性か」という重要な洞察(インサイト)を得ることができず、知識が断片化します。
1.2. 運用品質とセキュリティリスクのバラつき
個々のAIツールをスタッフが自由に選択・利用する環境は、属人化と管理リスクを生み出します。
- プロンプト技術の属人化: 優れた文章や分析結果を引き出す「プロンプト(指示文)」のノウハウが、特定のスタッフに集中し、組織内で共有・標準化されないと、業務の「質」が個人の習熟度に依存してしまいます。
- シャドーITとセキュリティ懸念: 事務局の承認を得ていない外部の無料AIツールが利用される「シャドーIT」が発生するリスクが高まります。学会の機密性の高い情報や個人情報が、適切なセキュリティ基準を満たさないツールに誤って入力されることで、情報漏洩や倫理的な問題を引き起こす懸念があります。学会運営におけるAI倫理的な配慮は、統合環境下で一元管理することで初めて担保されます。
これらの課題を乗り越えるには、データ、ツール、そして「人」が協働する「エコシステム」の構築が不可欠です。エコシステムとは、もともと生態系を意味する言葉ですが、ビジネスやIT分野では「複数の要素が相互に連携し合い、全体として価値を生み出す仕組み」を指します。
【参考】
・サイロ化とは?サイロ化によって生じる課題と解決策をご紹介|NTTデータ
・シャドーITとは?そのセキュリティリスクと対策方法をわかりやすく解説|NTT東日本
・ビジネスエコシステムの変化|総務省
2. 個別最適から全体最適へ:統合的AI活用環境がもたらす戦略的価値
個別業務における最適化がもたらした情報の「サイロ化」を乗り越え、学会運営の全体最適を図ることが、次なるAI活用の段階における重要な課題です。統合的なAI活用環境の構築は、単なる作業の省力化に留まらず、学会運営が蓄積する多様な情報を相互に連携させ、それに基づく洞察的・先見的な意思決定を可能にする「知(形式知・暗黙知)の基盤」を確立します。
これは、運営を経験則や慣習に委ねるのではなく、集積されたデータを客観的な根拠として活用することに繋がります。学術コミュニティの発展、公共的使命の達成、および会員へのサービス向上といった学会活動の質的向上を目指す、学術情報に基づく運営(エビデンス・ベースド・オペレーション)への転換を意味します。
この知の統合によって、事務局は個別タスクの処理から解放され、学会の中長期的な戦略立案という、より高度な知性が必要とされる役割へと進化(深化)することが可能となります。
2.1. 統一されたインターフェースとデータ連携の実現
理想的な統合環境が整えば、事務局スタッフは、日々の業務基盤(Google Workspace、Microsoft 365など)からシームレスにAI機能を呼び出せます。
例えば、以下のような複雑な作業の流れも、ツールを切り替えることなく完結します。
- Gmailで委員会出欠の返信メールを受信。
- Gemini for Google WorkspaceなどのAIアシスタントがメールを直接処理。
- その場で「未回答者リスト」を作成。
- Google スプレッドシート(会員管理データ)と自動で照合。
- リマインダーメールの下書きを生成。
さらに、この統合は将来的なAIエージェントの導入を見据えた強固な基盤となります。AIエージェントは、複数のタスクを自律的に判断し異なるシステム間を横断して実行可能です。
具体的には、エージェントが投稿者からの問い合わせ(チャットボット)、過去の査読記録(データベース)、最新の倫理規定(ドキュメント)を瞬時に連携させ、一貫性のある対応を自動で実行します。これにより、人の手を介さない高度なバックオフィス業務が実現します。キャップジェミニ(Capgemini SE:フランスの大手コンサルティング企業)の調査では、2026年までに82%の企業がAIエージェントを業務に組み込むと予測されており、学会運営においても無視できない重要な潮流です。
【参考】
・AIエージェントが企業を変える!2026年までに82%の導入が予測される未来戦略|Big Data Lab
・Who we are|Capgemini
2.2. 事例:AI協働による非効率業務の劇的な削減効果
統合環境の導入は、定型業務における人手作業を大幅に削減し、事務局の人的リソースを解放します。
例えば、学会大会や事務局への参加者からの問合せ対応業務は、学会運営の負荷が高い主要因の一つです。しかし、過去のFAQや会員情報を統合したAIチャットボットを導入することで、その件数は劇的に減少します。
- 問い合わせ件数の削減: AIチャットボットを導入した企業や組織の事例では、定型的な問い合わせ件数が、初期段階で約30%〜50%削減されるという結果が報告されています。さらに、FAQの一元管理とAI連携を進めることで、その削減効果は最大で90%以上に達する事例も存在します。
- リソースの再配置: 問合せ業務が半減することで、スタッフは捻出された時間を、投稿者へのきめ細やかなサポートや、より質の高いニュースレターの企画、そして学会戦略の立案といった、AIでは代替できない創造的かつ戦略的な業務に振り向けることが可能になります。
【参考】
・コールセンター×AI活用事例10選!54%対応時間を削減できた理由とは?|AI-FRONT-TREND
・チャットボット導入により約90%問い合わせ数削減へ|AI Messenger Chatbot
2.3. 戦略的な価値の創出:データドリブンな意思決定
統合環境の最終的な価値は、事務局が「タスクをこなす組織」から「データを活用し、未来を予測・設計する組織」へと進化することにあります。この「データドリブンな意思決定」の実現こそが、学会の持続的成長の鍵を握ります。
統合環境では、学会の運営データ(会員の属性、大会の参加率、問合せ傾向、ウェブサイトの閲覧履歴など)が一つに集約されます。
- 多角的分析による運営改善:統合環境は、大会後の満足度調査の自由記述(テキストデータ)と、大会運営中の問合せ件数(チャットボットデータ)を横断的に分析可能にします。例えば、「基調講演での同時通訳が聞きづらい」と「講演満足度が低かった回答」を瞬時に結びつけ、「次期大会では同時通訳システムと音響環境の方法を大幅に見直すべき」という戦略的な洞察を導き出します。
- パーソナライズされたサービスの提供: 会員データベースの属性情報(専門分野、役職など)と、ニュースレター記事の閲覧データ(クリック率)が連携することで、AIは「この会員が興味を持つ可能性の高い研究分野」を予測し、その会員向けに最適化された情報発信(パーソナライズ)を自動で提案できるようになります。これは、学会と会員とのエンゲージメント(参画意識)を高める上で不可欠な要素であり、運営情報のデジタル基盤統合を通じて実現される、学術サービス高度化の主要な成果の一つです。
個別業務のAI活用(個別最適)から、データと機能の統合(全体最適)への移行こそが、人的リソースの最適配分を実現し、学会の社会的価値の向上と持続的な発展を可能にする鍵となります。
【参考】
・コールセンター×AI活用事例10選!54%対応時間を削減できた理由とは?|AI-FRONT-TREND
・【生成AI×チャットボット】成功事例20選!失敗事例や効果的な導入のコツも紹介|SHIFT AI
・バックオフィスDXでどう変わる?各部門の進め方や連携に強いツールを紹介|マネーフォワード
3. 統合的AI活用環境への段階的ステップ
統合環境の構築は、いきなり大規模なシステムを導入するのではなく、既存の無料ツールや汎用AIを「接着剤」として活用しながら、段階的に実現していくのが、多くの学会にとって現実的かつリスクの低いアプローチです。
3.1. 既存ツールの「API連携」を活用した初期統合
まずは、現在利用しているツール同士を、API(Application Programming Interface)を介して連携させることから始めます。
- ローコード・ノーコードツールの利用: ZapierやIFTTTといった「ローコード・ノーコード」の自動連携ツールは、専門知識がなくても、「もしGoogle Formsで申込があったら、Slackの事務局チャンネルに通知し、同時に会員管理用のGoogle スプレッドシートに転記する」といった、単純なRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を構築できます。また、Base44やReplitなどは、特に近年注目されている「AI駆動型の開発」という新しい分野のツールとして台頭しています。
【簡略版:Zapier連携の実装フロー】
トリガー:Google Formsに新規回答
↓
アクション1:スプレッドシートに自動追加
↓
アクション2:OpenAI APIで内容要約・緊急度判定
↓
アクション3:Slackに通知
無料版制限:月100タスクまで(中小規模学会なら十分対応可能)
- AI機能の組み込み: この自動連携のフローに、OpenAIやClaudeなどのAIのAPIを組み込むことで、さらに高度な自動化が可能です。例えば、「フォームで自由記述の意見が来たら、その内容をAIに要約させ、感情分析で緊急度を分類してから通知する」といった仕組みを構築できます。これは、人間の判断が必要な業務のみをスタッフに回す「AIフィルター」としての役割を果たし、工数削減率を向上させます。
3.2. 特化型AIツールの「エコシステム」への組み込み
統合環境は、汎用AIだけでなく、翻訳(DeepL)、文法チェック(Grammarly)、議事録作成(Otter.ai)といった特化型AIツールを、学会のワークフローの「標準機能」として位置づけ、組織全体で活用することが重要です。
- ワークフローの標準化: 例えば、「国際委員会での議事録は、Otter.aiで文字起こし後、DeepLで翻訳し、その結果を必ず共有ドライブに格納する」という標準的な運用ルールを確立します。このルールこそが、バラバラに存在していたデータを、統合環境のナレッジベースに集約するための「仕組み」となります。
- AIの共同利用環境の整備: Microsoft 365やGoogle Workspaceのエンタープライズ機能に搭載されているAIアシスタントを導入することは、すべてのスタッフが同じ品質とセキュリティ基準でAI機能を利用するための最も効率的な方法です。これにより、個人のスキルに依存しない、組織的なAI活用が促進されます。
まとめ
学会事務局におけるAI活用は、単に個別のタスクをAIに代行させるという段階から、データ、ツール、そして「人」が協働するエコシステムを整えるという、次なる段階へと進化(深化)していきます。
この統合的なAI協働環境の構築は、個々の業務における効率化(問い合わせ件数の最大90%削減など)を確定的なものにするだけでなく、学会が蓄積してきた貴重な運営情報を「戦略的資産」へと変貌させるでしょう。
事務局は定型業務から解放され、人間にしかできない活動に注力できます。会員への個別的な配慮、研究公正への徹底した対応、学術コミュニティの未来を創造する戦略立案。これらの付加価値の高い業務こそが、事務局の本来の役割です。
この「統合環境への気づき」と「段階的な移行」が、学会事務局の持続的発展と学術コミュニティ全体の活性化に向けた、今後の運営戦略の核となります。
【参考】
・【Tips】学会ごとに異なる投稿規定への対応と、投稿者への配慮ある提案方法|本連載記事のTips参照
学術大会・国際会議開催システム「アワード」のご紹介
学会運営における課題を解決し、効率的かつ効果的な運営を実現するために、学術大会・国際会議開催システム「アワード」は以下のニーズにお応えします。
-
1. 学会の効率化と人手不足の解消
学会運営では、事務局の業務量が膨大で、少人数で対応するのが難しい場合もあります。学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、煩雑な運営業務を自動化・効率化することで、人的リソースの負担を軽減します。たとえば、参加登録、プログラム作成、講演者管理などがワンストップで完結します。
-
2. 学会運営のコスト削減
学会開催には、印刷物や郵送、事務局人件費など多くのコストが発生します。学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、クラウドベースでの運営によりこれらのコストを大幅に削減可能。さらに、事務局代行費用を削減しつつ、高品質なサービスを提供します。
-
3. 決済機能でスムーズな収益管理
学会参加費や年会費のオンライン決済に対応。安全性の高い決済システムを導入しているため、事務局での入金確認の手間が省け、効率的な資金管理が可能です。これにより、参加者にも事務局にもストレスフリーな学会運営を実現します。
-
4. 学会運営サポートで「大変」を「簡単」に
「学会運営が大変」と感じている学会事務局の方々に向け、運営全般を支援する学会運営サポートをご用意しています。例えば、会場手配、プログラム編成、スポンサー管理など、運営代行サービスもご紹介可能です。
-
5. 柔軟な管理システムで多様なニーズに対応
学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、学会の規模や形式に応じて柔軟にカスタマイズ可能。オンライン学会、ハイブリッド開催にも対応しており、参加者がどこにいても円滑な学会開催をサポートします。
-
6. 費用対効果の高い学会開催を実現
学会開催費用を抑えつつ、質の高い学会運営を目指す方に最適なソリューションです。クラウド型システムの導入で初期費用を抑え、必要に応じて追加オプションを選択することが可能です。
学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、学会の運営をトータルでサポートし、効率化・コスト削減を実現する強力なパートナーです。学会運営の課題を抱える事務局や運営会社の皆さま、ぜひ一度ご相談ください!





