ChatGPTのAI判定ツールを使った修士論文判定
2023.03.20
2025.11.20
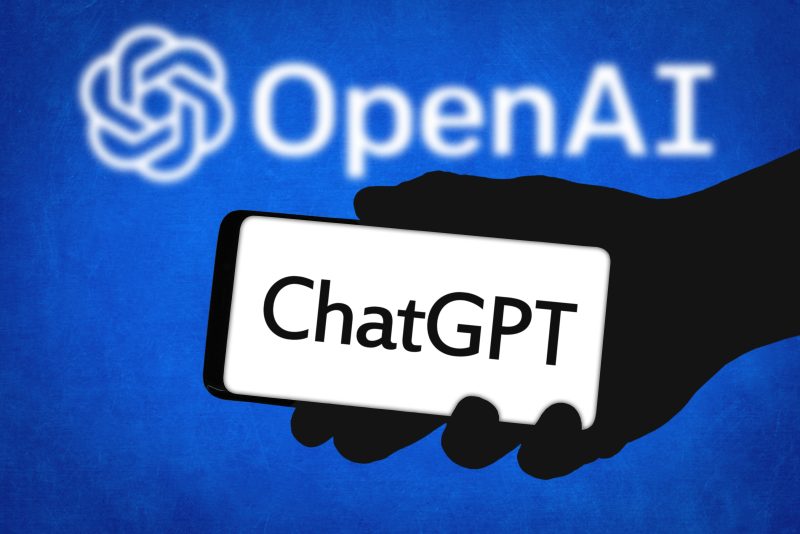
Chat GPTが話題となり様々な利用方法が考えられる中で問題点も浮き彫りになってきました。その問題点の1つを解決してくれるのがAI判定ツールです。この記事では、Chat GPTのAI判定ツールについてご紹介していきます。
Chat GPTが作成した偽論文の要旨は精度が高い
OpenAI社がリリースしたChat GPTが生成した偽文章はかなり精度が高いそうです。最新の研究では、Chat GPTが生成した文章を科学者らが3回に1回の割合で本物の論文だと間違えたということが明らかになっています。
不気味さも感じられるほど人間に近い文章を作れるChat GPTは、人工知能と人間の未来について議論を生んでいます。
AI判定ツールとは
Chat GPTなどのチャットボットが発達している中で、AIで作られた文章かどうかを判定するAI判定ツールが重要視されつつあります。
その中でChat GPTを生み出したOpen AI社がAIプログラムによって書かれた文章を判別してくれるAI判定ツールを公開しました。classifier(クラシファイアー)と命名されたこのツールは、Open AI社製の製品以外でも検知することができるものです。
なお、このclassifier(クラシファイアー)には幾つかの限界があり100パーセントの判断を下す手段ではなく1つの判断基準として利用すべきとされています。
理由としては、まだまだ精度が高いとは言えないからです。Open AI社が実施したclassifier(クラシファイアー)の評価実験ではAIが作り出したテキストのうち正確な判定をできたのは26パーセントにとどまっており、人間が書いたテキストの9パーセントをAIが作ったテキストと判断してしまいました。
Chat GPTは、人気を集め利用者もどんどん増えて行く中で学生がレポートや課題を生成するために利用するケースも増えていくと考えられます。
AI文章判別ツールの問題点
AI文章判別ツールは、判別機能が備わってはいますが性能はあまり高くありません。
判別ツールは、基本的にネット上に公開されている膨大なテキストデータを対象に学習させたAI言語のモデルでありAIによる文章の生成された可能性があることを予想できるようにしたものです。トレーニング中にAI文章判別ツールは、ウェブサイトやその他のソースから人間が書いた文章と比較し、文章の出所を示すパターンを学習しようとして精度を上げていきます。
しかし、AI文章判別ツールの精度が上がるとともにAIが生成する文章の質も同じように上がっていくでしょう。継続的にAI文章判別ツールは、トレーニングを続けていかなければ時間の経過とともに精度が下がっていくことになります。
そうなっていくと丸々AIが生成した文章では、わかってしまう未来が来る可能性も高いですが、AIが生成した文章に少し手を加えて整えればどのような判別ツールでも通り抜けることも可能でしょう。文章作成をするAIツールの進歩とそれを使う人が成長していくことにより、AI文章判別ツールが進歩しても永遠のイタチごっこになってしまう可能性があります。
AI文章判別ツールは、今の段階で役に立つ場面が多くあるでしょうがAIによって生成された文章であるという絶対的な証拠になりえるかといったら確実に信頼できるものではないでしょう。
AIが作成した文章をめぐる問題を解決するための完璧な特効薬は現段階では無く、今後も現れない可能性が高いです。
修士論文などの判定はできるのか
現段階で100パーセント、見抜くというのは難しいようです。1行でもAIが作った文章が入っていればAI文章作成ツールを使ったと判断されてしまうこともありますし、全部AIが文章を作ったとしても言い回しを変えて、言葉を変えて校正しなおせば人間が書いた文章と判断されてしまうこともあります。
AI文章作成ツールを使い修士論文を作る側が、しっかりとファクトチェックをし判別ツール対策を行えばおそらく判定することは難しいでしょう。修士論文を作る側も言い回しが考え付かずたった1行をAIに助けてもらっただけで、AIが作った修士論文として判定されてしまい却下されてしまうのはかなりきついです。
また、100パーセント人間が書いた文章でも判別ツールは間違ってAIが作った文章だという判断を下してくる可能性もあります。判断の補助的なツールとして使うのならば問題はないと思いますが、現段階でもこれからの未来でもAI文章判別ツールが工夫を凝らしたAI文章を100パーセント判断するのは難しいと言えるでしょう。
参考URL
- ChatGPT作のニセ論文要旨は1/3の割合で査読者に本物だと思わせる(Forbes JAPAN) – Yahoo!ニュース
- ChatGPTのAI判定ツールを使って学生の修論を判定してみた:情処ラジオ – YouTube
- ChatGPT開発企業、AIが書いた文章の判別助けるツールを公開 – Bloomberg
- 【実験】OpenAI、GPTZero…AIが書いた文章はどれぐらい見抜かれる?7つのAI判別ツールを比べてみた【テッククランチ】 | レバテックラボ(レバテックLAB) (levtech.jp)
- AIの文章を判別するアプリ、発明した学生に称賛集まる。「論文ポリスかよ」と不満訴える学生も… (buzzfeed.com)
学術大会・国際会議開催システム「アワード」のご紹介
学会運営における課題を解決し、効率的かつ効果的な運営を実現するために、学術大会・国際会議開催システム「アワード」は以下のニーズにお応えします。
-
1. 学会の効率化と人手不足の解消
学会運営では、事務局の業務量が膨大で、少人数で対応するのが難しい場合もあります。学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、煩雑な運営業務を自動化・効率化することで、人的リソースの負担を軽減します。たとえば、参加登録、プログラム作成、講演者管理などがワンストップで完結します。
-
2. 学会運営のコスト削減
学会開催には、印刷物や郵送、事務局人件費など多くのコストが発生します。学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、クラウドベースでの運営によりこれらのコストを大幅に削減可能。さらに、事務局代行費用を削減しつつ、高品質なサービスを提供します。
-
3. 決済機能でスムーズな収益管理
学会参加費や年会費のオンライン決済に対応。安全性の高い決済システムを導入しているため、事務局での入金確認の手間が省け、効率的な資金管理が可能です。これにより、参加者にも事務局にもストレスフリーな学会運営を実現します。
-
4. 学会運営サポートで「大変」を「簡単」に
「学会運営が大変」と感じている学会事務局の方々に向け、運営全般を支援する学会運営サポートをご用意しています。例えば、会場手配、プログラム編成、スポンサー管理など、運営代行サービスもご紹介可能です。
-
5. 柔軟な管理システムで多様なニーズに対応
学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、学会の規模や形式に応じて柔軟にカスタマイズ可能。オンライン学会、ハイブリッド開催にも対応しており、参加者がどこにいても円滑な学会開催をサポートします。
-
6. 費用対効果の高い学会開催を実現
学会開催費用を抑えつつ、質の高い学会運営を目指す方に最適なソリューションです。クラウド型システムの導入で初期費用を抑え、必要に応じて追加オプションを選択することが可能です。
学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、学会の運営をトータルでサポートし、効率化・コスト削減を実現する強力なパートナーです。学会運営の課題を抱える事務局や運営会社の皆さま、ぜひ一度ご相談ください!





